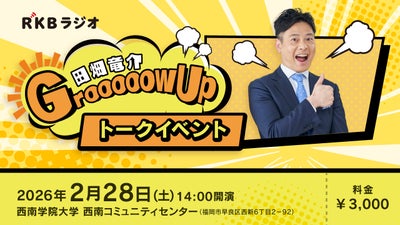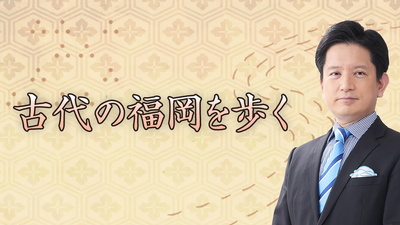日本テレビ系の人気バラエティー番組『月曜から夜ふかし』で、街頭インタビューに応じた中国出身の女性の発言が、事実と異なる形で編集され、放送されたことが発覚した。東アジア情勢に詳しい、元RKB解説委員長で福岡女子大学副理事長の飯田和郎さんが4月7日のRKBラジオ『田畑竜介 Grooooow Up』に出演し、「ステレオタイプな中国像を安易に利用したもの」と批判した。
問題の本質:安易な面白さ追求と異文化への配慮欠如
放送局が伝える情報は、それを視聴する人に大きな影響を与える。特に、その放送内容が日本以外の外国、外国人を対象にした場合、それぞれの国民同士の感情に摩擦が起きたり、時には国際問題に発展したりすることもある。
日本テレビ系のバラエティー番組『月曜から夜ふかし』の中で、街頭インタビューに応じた中国出身の女性が、中国でカラスがあまり飛んでいない理由として、「みんな食べてるから少ないです」「とにかく煮込んで食べて終わり」など、発言していない内容を、発言したかのように編集し、放送していたことがわかりました。
この番組は、3月24日に放送されました。日本テレビの福田博之社長は3月31日の定例会見で、「演出の範囲を超え、あってはならないことだ」と述べ、謝罪しました。
日テレの社長が謝罪した3月31日は、フジテレビの問題がクローズアップされた日と同じ。第三者委員会は、元タレントの中居正広氏から元女性アナウンサーが「性暴力の被害を受けた」と認定。委員会の報告書は、フジテレビ経営陣の責任や企業風土を厳しく指摘した。
この日は、中居正広氏を巡る報道一色だった。ただ「中国人はみんな食べているから、中国にはカラスは少ない」というこのねつ造も、国際報道に携わってきた私には大きな問題点を抱えていると思う。それは日本と中国という「国を跨ぐ」問題も絡むからだ。
編集はいわゆる「切り取り」だ。つまりインタビューを受けた中国出身の女性が、カラスの話題とは別の場面で、「みんな食べてるから少ない」、また「とにかく煮込んで終わり」と喋った映像を切り取って、その女性が「中国ではカラスを食べる」と発言したようにしていたわけだ。ているという。
このコーナーの担当テレビディレクターは日テレによる聞き取りに対し、「より面白くしたかった」「差別的な意図はない」と述べているという。その言葉を信じたい。『月曜から夜ふかし』はテンポが速く、内容も面白い。私も好きな番組だ。ただ、「差別的意図はなかった」にしろ、「中国、中国人を扱う、この種のネタは視聴者にウケる」「視聴率を稼げる」という潜在的な思いがなかっただろうか。そして、このディレクターに限らず、こんな情報を受け入れる側の私たちにもないだろうか。
背景にある中国へのステレオタイプな視点
バラエティー系の番組で、中でも海外の話題や外国人を取り上げる場合、中国という国との文化の違い、中国人の失敗談…、いわゆる「中国あるある」を映像とともに紹介する番組を、よく見かけるような気がする。多くは「あざける」「あざ笑う」トーンが目立つように思える。
たとえば、「5人乗りの乗用車に、なんと15人も乗って公の道路を走り、警察に検挙された」、また「幼い子供が細い管にスポッと落ちてはさまれた。数十時間後に救助された」…というような話。「なんでルールを守らないんだ」「なんでそんな危ないところに幼児を放置するんだ」ということだ。
これらは実際に起きた話のようだ。ただ、紹介した、中国人女性が「中国ではカラスを食べる」という趣旨の発言をしていないのに、発言したかのように編集された今回のケースは、同じトーンの延長線上にあるのではないか。私が感じるのは、「やっぱり中国は、中国人はダメだよね」という番組の作り手の狙い、それを観て、ウンウンとうなずいてしまう一部の人たち、留飲を下げる人たち――「中国なら、中国人なら、茶化していい」そんな番組の作り手、受け手の構図だ。
文化の違い、国の発展レベルの違いによって、ほかの国でも、我々日本人には奇妙に映る話題はあるだろう。だが、そのような国々とは別に、我々が抱く中国に対する認識が関係していないだろうか。「中国だけの」という背景だ。
中国はずっと貧しい国だった。マラソンに例えると、中国という選手は、日本のずっと後ろを走っていて、姿さえ見えなかった。その中国を、日本の政府や企業が支援したこともあって、中国は成長を続けた。一方、日本の成長は頭打ち。日本と中国というマラソンランナーの差はどんどん縮まった。
そして、中国という選手に、日本という選手は追い抜かされた。名目GDP(国内総生産)で中国が日本を追い抜いて世界2位になったのは2010年だ。日本はドイツにも抜かれて世界4位。今やGDPで5位のインドが迫っている。
GDPが世界2位になっても、確かに中国は先進国とは言えない。ただ、「こんなはずじゃなかった」という思いが、我々日本人の中にないだろうか。そして、片や、中国は国の力が付くにつれ、自信を持ち、時には過信と思える振る舞いを、国際社会で繰り返している。一般市民に中国社会の間でも、「俺たちの方が日本よりずっと上だ」という思いが広がっている。
日本からすると、苛立ちと焦燥。つまり、イライラする気持ちと、焦る気持ちが混在していないか。そんな隣の国・中国を茶化す、イジると、一時でも、痛快に思う人がいるのではないか。
そういう流れの中で、日本ではいわゆる「中国あるある」「オモシロ中国」といったトーンのテレビ番組がつくられ、それがウケる。そして今回のような、「中国出身者が『中国人はカラスを食べる』と証言した」というねつ造につながったのではないだろうか。
カラスは害鳥。「カラスを食ってるのか、ダメだよなあ」という話になる。テレビだけでない。「中国人を茶化す」「中国をあざ笑う」内容の出版物も多く登場し、YouTubeでも、そんな動画が再生回数を稼ぐ。
総務大臣も苦言:メディアの責任と国際関係への影響
このコーナーでも紹介したことがあるが、日本と中国それぞれで、「相手の国をどう思うか?」という世論調査を実施すると、日中どちらでも9割近い人が「相手国に対してよくない印象」を持っている状況が明らかになっている。今の中国側にも問題はあるが、日本国内にも、問題はないだろうか。その一つの例が、取り上げた「ステレオタイプの中国話」ではないか。
日本に住む中国人は多い。『月曜から夜ふかし』を観ている中国人も多いだろう。そのためか、中国人女性が「中国ではカラスを食べる」と発言したかのようにねつ造していた場面を観て、中国人の使うSNSで指摘され、中国でも火が付いたという。
放送行政を管轄する、総務省の村上誠一郎大臣は記者会見で、日テレの番組に触れ、このように苦言を呈した。
日本テレビは正確な情報発信を行い、国民の知る権利を満たすという放送事業者の社会的役割を自覚して、適切に対応していただきたい。
総務大臣の言葉は、誤った情報への苦言とともに、中国との2国間関係を損なわないようにとの思いもあるのだろう。偏った認識に基づいて、隣国を茶化しても、ましてや、ねつ造した情報を、電波を使って流しても、メディアは自らの首を絞めるだけだ。何より、自らを貶めるだけでしかない。
この記事はいかがでしたか?
リアクションで支援しよう