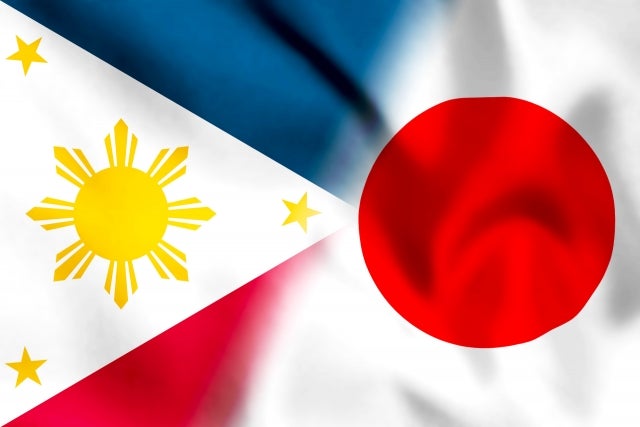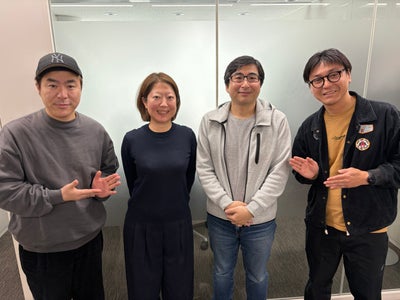8月25日放送のRKBラジオ『田畑竜介 Grooooow Up』に、東アジア情勢に詳しい元RKB解説委員長で福岡女子大学副理事長の飯田和郎さんが出演し、8月最後の「戦後80年」シリーズとして、フィリピンに残された日本人孤児の問題と、私たちが向き合うべき「戦後」の課題について語りました。
忘れられた「戦後」の課題
日本の周辺の国や地域にとっての「戦後80年」を4週間にわたってシリーズで考えてきました。中国、台湾、そしてモンゴルを取り上げてきましたが、最終回となる今回は、フィリピンに残された「日系2世」の問題から、日本が戦後80年間、向き合い続けてきた課題について考えたいと思います。
先日、フィリピンに残された日系2世の竹井ホセさん(82歳)が、戦後80年を経て初めて日本を訪問し、親族との対面を果たしたというニュースがありました。日本国籍取得に向けた調査のため、日本政府が訪日費用を初めて負担したケースであり、このニュースは私にとって、この夏で最もハッとさせられるものでした。
私は合わせて10年間、海外特派員を経験しましたが、日々の国際情勢を追いかけるだけでなく、その土地で活動してこそ取材が可能なテーマがあります。かつて中国に駐在していた私は「中国残留日本人孤児」の問題にこだわりを持っていましたが、東南アジアでも同じです。
かつて日本が周辺国へ押し出していき、日本人が拠点を築き、戦争に敗れた後、帰国できた人もいれば、現地で亡くなった人もいました。その土地に、とりわけ幼い子どもたちが残されたのです。
「父系血統主義」が残した傷跡
竹井ホセさんは現在82歳。日本の敗戦時にはわずか2歳でした。敗戦の2年前、1943年に日本人の父親とフィリピン人の母親の間に生まれ、父親はフィリピンで鉄道技術者として働いていました。父親は竹井さんが母親のお腹の中にいる時に消息不明になりましたが、後に軍人として日本に帰国していたことが判明。調査を経て、大阪に親族が住むことがわかり、今回の訪問で父親の墓参りをし、異母兄弟との対面を果たしました。
竹井さんは早期の日本国籍取得を願い、「年齢的に自由に動けることが少なくなりました。早く、かなうことを願っています」と語っています。
フィリピンには戦前、鉄道などのインフラ建設や農園経営のために多くの日本人が移住しました。日本人男性と現地の女性の間に生まれた「フィリピン残留日本人2世」の総数は、亡くなった方を含めて約3800人。今も存命の方のうち、約50人が日本国籍の取得を望んでいるといいます。
かつての戸籍制度には「父系血統主義」というものがありました。父親が日本国籍を持ち、母親が外国籍の場合、「生まれた子供は日本国籍」と定めた制度です。現在は改定されていますが、竹井さんのケースは、この「父系血統主義」に則れば明らかに日本人なのです。
しかし、かすかな記憶やわずかな手掛かりだけで、「自分は日本人である」と証明するのは困難な作業です。日本で新たに戸籍を作るためには、断片的な情報だけでは出生に関する証拠書類を集めるのが難しく、戦後80年という時間の壁が立ちはだかっています。
「祖国」で直面する現実と私たちの問題
念願叶って日本国籍を取得し、日本に帰国しても多くの問題が存在します。彼らにとって「祖国ニッポン」ではありますが、経済的な問題や言葉の問題が立ちはだかります。これは中国残留日本人孤児の2世、3世も同じことが言えます。環境に馴染めず、孤立して道を外してしまうケースも少なくありません。
そこには何より、私たち受け入れる側の問題も存在するように感じます。彼らを「よそ者」として異端視する風潮が今も存在しないでしょうか。一方で、7月の参議院選挙でも見られたように、「日本という国」、また「日本人」をことさら強調する人たちがいます。それは「日本人の血」「日本民族の血」といった血統主義につながるかもしれません。
血統主義は、昔も今も、多くの過ちを犯してきました。現地で生まれた在留孤児2世、3世は、一部の人たちが言う「日本人」ではないのでしょうか。彼らもみんな日本人なのです。狭義の血統主義は改めるべきです。
戦後、フィリピンをはじめアジアの国々では反日感情が激しく、日本人としての出自を持つ人々は、その出自を隠して暮らさざるを得なかった人も多かったはずです。
この8月、私はこのコーナーで、日本の周辺の国や地域にとっての「戦後80年」をシリーズで4回にわたり紹介してきました。毎日何気なく見ている福岡の博多港にも、終戦後、大陸から引き揚げてきた多くの日本人を乗せた船が着いたという歴史が詰まっています。
戦後80年が経っても、今なお「戦前から続く、それぞれの戦後」を生きている人々が、日本にも、周りの国々にもいることを、私たちは忘れてはいけません。そして、今を生きる私たちにできることは何かを、強く感じる2025年の8月です。
この記事はいかがでしたか?
リアクションで支援しよう
この記事を書いたひと

飯田和郎
1960年生まれ。毎日新聞社で記者生活をスタートし佐賀、福岡両県での勤務を経て外信部へ。北京に計2回7年間、台北に3年間、特派員として駐在した。RKB毎日放送移籍後は報道局長、解説委員長などを歴任した。2025年4月から福岡女子大学副理事長を務める。