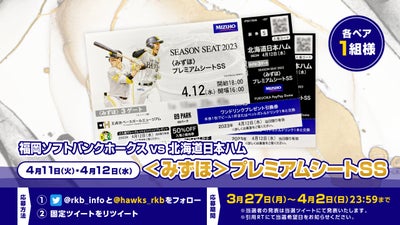♪うさぎ追いしかの山 小鮒釣りしかの川 ♪の唱歌「故郷」。日本人の心にきざまれたこの歌を作詞した国文学者の高野辰之(明治9年~昭和22年)の生まれ故郷が、長野県中野市です。高野辰之は、ほかにも「朧月夜」「春の小川」「春がきた」「もみじ」なども作詞しています。作品のベースとなった風景は、生まれ育ち、また一時期教鞭もとった北信濃の中野や飯山のものであり、今もそれを感じることができるのです。高野辰之記念館副館長の小林雅美さんは、高野の妹のお孫さん。


「“故郷”に高野が描いた風景は日本中どこにでもある、そして誰もの心の中にある風景だけれど、やはり本人にとっては子供の頃から見てきたこの風景を想いながら書いたのだと思います」と教えてくださいました。そして「記念館の2階からも”かの山”が少し見えますよ」と。かの山とは大平山(おおひらやま)と大持山(だいもちやま)。
記念館から高野の生家を超えて10分ほどのところに「ふるさと橋」があり、2つの“かの山”とその裾野に広がる棚田、そして“かの川”である斑川(はんがわ)が一目で見えるのです。


私は♪うさぎ追いし♪は、野山でうさぎを追っかけっこしていた日々のことだと思ってましたが、小林副館長曰く「この辺りでは大正時代頃まで“ウサギ追い”という冬の行事があったんですよ。除雪のない時代、子供達をつれて山奥までは入れませんから、すぐそこでね。地区の人達もみな一緒にウサギを追って、漁師さんが撃ったのを獲って、みんなで食べたわけです。貴重なタンパク源でしたから」と。おおおっ!昔、先生に「♪うさぎ“おいしい”♪ではありません!追いし!追いかけたという意味ですよっ。」と、がっつり言われてましたが、“おいしい”も誤りではなかったのだ…。衝撃を受けていると「あの…。私、ウサギ追いやったことあるんです」との声。主は、この日の案内役・長野県観光振興課の丸山澄夫さん。高野辰之と同じ中野市出身かつ在住の昭和39年生まれです。「えげげげっ!?」と心底びびる私に「中学校の頃、ふるさと体験授業で“ウサギ追い”を全校生徒250人くらいでやったんです。かんじき履いて、横一列に並んで、『ぱんぱんぱんぱん』手とかで音を鳴らしてびっくりさせて、山のふもとへ向かってウサギを追い込むんです。ある程度追い込んだところで、同行していた猟友会の人がバンと撃っちゃうんですよ。」いやあ、知らなかった…。だから旅は、出逢いは、おもしろい。


「朧月夜」の♪菜の花畑に入り日薄れ♪の菜の花、当時は菜種油のための菜の花だったと思われますが、今はお隣の飯山市が野沢菜の花でその姿を見せてくれます。2番の♪カエルの鳴く音も鐘の音も♪の鐘は、中野の真宝寺の鐘。「春の小川」の♪さらさら行くよ♪の歌詞は、もとは♪さらさら流る♪だったのが書き直されたもの。天皇陛下は“流る”、美智子皇后陛下は“行くよ”で習われたそうで、ある学年以上は違う歌詞で記憶なさっているのだそう。また「春が来た」は♪山に来た 里に来た 野にも来た♪ですが、曲がつく前は山→野→里の順だったそう。メロディに合わせて書き直されたとか。小林副館長にいっぱい教えてもらいました。
余談ですが、この中野市、「カチューシャの歌」「ゴンドラの歌」「シャボン玉」の作曲者である中野晋平のふるさとでもあり、映画音楽の第一人者で宮崎駿作品や北野武監督作品の音楽を手がける久石穣さんの出身地でもあるんですって~。
□ 高野辰之記念館 → http://www.city.nakano.nagano.jp/tatsuyuki/index.htm
□ 信州なかの観光協会 → http://www.nakanokanko.jp/
この記事はいかがでしたか?
リアクションで支援しよう