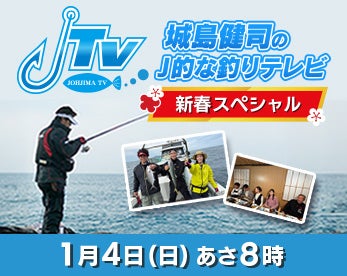7月豪雨「民陶の里」で多くの窯元が被災 土砂に埋もれた「資さんうどん」のどんぶり
九州北部を襲った7月10日の大雨で、福岡県東峰村では「小石原焼」の窯元42軒のうち、11軒が被災しました絶望感も漂う現場。それでも前を向こうとする人たちがいます。
目次
6年前の豪雨でも同様の被害に…

東峰村にある小石原焼の窯元は42軒。そのうち11軒が土砂が流入するなどの被害を受けました。「秀山窯元」もその1軒です。山からの土砂と雨水が工房の中に流れ込み、足を踏み入れる事さえできない状態に。実は、2017年の九州北部豪雨でも同じ被害に遭っていたのです。その後、工房の裏山には砂防ダムが建設されましたが、土砂は再び工房に流れ込みました。
秀山窯元 里見武士さん「村も県も『これで相当な豪雨が来ても耐えうるだろう』という“お墨付き”をいただいたんですけど、またこういう状態なので……」
焼き物の機材は失われても

大雨から一か月。ボランティアによる復旧活動が進み、8月15日(火)に焼き物作りを再開できるところまでこぎつけました。しかし、その代償は小さくありません。
秀山窯元 里見武士さん「電気を通しましたけど、動かない状態ですね」
商売道具のろくろは買い替え、土砂に浸かった窯の修理などで、再開までにかかった費用は500万円を超えます。
秀山窯元 里見武士さん「一度災害で機材は奪われるんですけど、何十年と培ってきた技術と目があります。それは失われることはないので、また新たにいい作品を作れれば、と切に思う」
山とともにある焼き物作り

小石原焼は、東峰村の最も大きな産業。毎年行われる小石原焼きのイベント「民陶村祭り」には焼き物目当てに多くの人が訪れます。
その窯元が、2017年の九州北部豪雨、さらに2023年7月の大雨と、山の土砂に襲われてきました。そこには、「山」と「焼き物づくり」の切っても切れない関係がありました。
小石原焼陶器協同組合 元永彰一代表理事「緩やかな坂に“登り窯”を造るので山麓、山にかかったところが一番適している」
斜面を利用し一度に大量の作品を焼くことができる「登り窯」は、山のふもとに多く作られてきました。東峰村には質のいい土や水など焼き物作りに欠かせない要素が揃っていたため、窯元が集まり発展してきました。そこに、想像を超える量の雨が降るようになり、窯元への被害が続いているのです。
小石原焼陶器協同組合 元永彰一代表理事「ひょっとしたら災害の始まりかもしれない。もし来年も大雨が降ったらどうしよう、と自然に対しておののくばかり。大雨がないことを祈るだけ」
「大雨に強い里山づくり」の取り組み

この大雨による災害を黙って見ているわけではありません。九州北部豪雨以降、力を入れているのが山の管理です。
里山保全の会東峰フラワーズ 柳瀬弘光代表「林が真っ暗で、間伐を進めないと。ひょろっとした細長い杉になっているので倒れやすく、根の張りも浅い状態」
東峰村で果樹園を営む柳瀬弘光さんは、農家や陶芸家など村の有志を集め、里山の間伐を行っています。手入れが十分でない山では、細い杉が密集し、根の張りが浅くなり土砂崩れが起きやすい山になります。
そこで杉の生えている間隔を広げる間伐を行い、一本一本の木の根を深く張らせることで、土砂崩れの起きにくい地盤に改良しているのです。さらに、落葉広葉樹を植えることで、スポンジのように多くの水を蓄えられる「大雨に強い里山づくり」を進めています。
里山保全の会東峰フラワーズ 柳瀬弘光代表「東峰村のような山間地では、山の手入れをしないとどこが崩れてもおかしくない。次の世代にどういった環境を残していくのかは、今生きている大人の責任があると思う。少しずつでも活動を続けていきたい」
葛藤しながらの復旧作業

九州北部豪雨から6年。「100年に一度起きる大雨」と呼ばれた災害がまた起きました。大雨から1か月、窯元は葛藤しながらも前を向きます。
小野窯元 小野妙子さん「毎日『頑張ろう』という気持ちと、『どうしよう…』とくよくよとなる気持ちとが戦っています。『涙が枯れたかな』と思うのだけど、きょうもボランティアがたくさん来てくれていたので、やはり涙が出ます。同業者からは『しばらくは窯を貸してあげてもいいよ』と明るい話があったし、ランティアが暑い中で自分たち以上に活動してくれるので、『自分たちがへこたれていたら申し訳ないな』という気持ちで、毎日少しずつ復旧活動をしています」
この記事はいかがでしたか?
リアクションで支援しよう