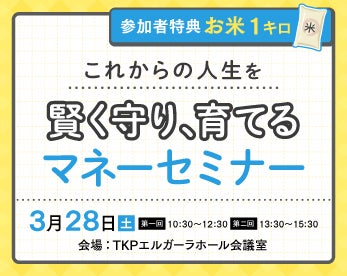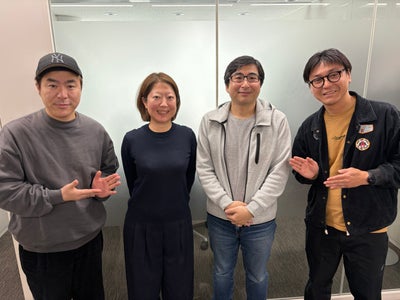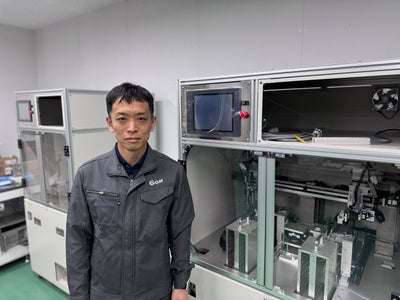9月に入っても猛暑日が続く異常な暑さとなっていますが、危険な暑さの中で外に出るのもリスクがあるということで、エアコンのきいた家の中や図書館などで読書をする人も多いようです。本は、文章を書く作家や詩人がいて、表紙のデザインを手掛ける専門家がいて、印刷や製本を経て本屋さんに並ぶわけですが、このたびその常識をちょっと超えた詩集が福岡で出版されて話題になっています。9月5日放送のRKBラジオ『立川生志 金サイト』に出演した毎日新聞出版社長の山本修司さんが解説しました。
装幀家という仕事
本ができるまでにはさまざまな工程があります。作家が文章を書いて、ただそれを束ねてみたところで、それは本とはいえません。表紙やカバーがあって初めて本という形になります。
表紙やカバーのデザインを手掛ける専門家を装幀家(装丁家)といいます。英語の「ブックデザイナー」という呼び方の方が分かりやすいのかもしれませんが、私は装幀家の仕事に心から敬意を持っていて、ブックデザイナーではちょっと薄い感じがしますので、常に装幀家と言っています。
作家と装幀家がいて本になるわけですが、今回、詩人と装幀家がコラボして、つまり同じ土俵に乗って作った画期的な本が出ましたので、これを紹介したいと思います。
『プリズンブレイク 脱獄』という詩集なのですが、山口県下関市在住の詩人・北川透さんが詩を書き、福岡在住の装幀家、毛利一枝さんが表紙やカバーのデザインを担当したのですが、北川さんの求めで、毛利さんが撮った写真約50枚が掲載されて、これが対等な関係で掲載されているので「詩と写真集」となっているのです。
表紙には普通なら北川さんだけの名前が出て、裏表紙などに「装幀・毛利一枝」と書かれるのですが、「北川透 写真/毛利一枝」と共作になっています。出版社は福岡市にある書肆侃侃房です。
この本の内容に触れる前に、装幀家という仕事について説明しておきます。出版社は、編集者が作家さんらから原稿をもらって、それを印刷会社に送って印刷・製本されるという過程を経るのですが、表紙やカバー、それから「帯」と呼ぶ、その本の内容や推薦文などを書いたものを編集者が装幀家に頼んで本に合うように作って、最終的に本の体裁となっています。
装幀は本の顔ですから、そのカバーのデザインによって読者の興味をひいて書店で手に取ってもらえるかどうか、要は売れ行きにかかわりますので、とても重要です。
レコードやCDをジャケットのデザインで買う「ジャケ買い」という言葉がありますが、「表紙買い」という言葉もあります。毎日新聞出版が発行している週刊誌『サンデー毎日』も、先週号は「THE ALFEE」を表紙にしたのですが、いつもよりもずいぶん売れ行きがよく、根強い人気を再確認したところでした。
装幀家にはデザイン力は言うに及ばず、著者の思いやその本の意義、魅力といったものをくみ取って表現することが求められますし、カバーにどんな紙を使うかなど、本作りにかかわる知識も必要で、何よりも本に対する愛情が欠かせません。
著者や編集者とのコミュニケーション能力、幅広い教養も加えた人間としての総合力が問われる仕事といっても過言ではないのです。私が装幀家を尊敬しているのはそんなところからで、今回の詩集を手掛けた毛利さんもすごい教養の持ち主で人脈も広く、とてもチャーミングな女性です。
詩と写真の融合:『プリズンブレイク 脱獄』
私が今日ご紹介したい『プリズンブレイク 脱獄』という本は、90歳になる北川透さんの最新詩集なのですが、この方は詩を作ることに加えて、評論の分野でも60年以上にわたって活動を続けています。その言葉はものすごいパワーを持っていて、批評の鋭さは刃物を突きつけるような激しさも持ち、社会や他者だけでなく、自身にも向けられます。
詩の中にもそれはみられて、例えば『破片』という詩では「いつか 詩が書けなくなる なんて 思わないようがいい おまえが 書いたものなど 詩であったことはなかった」という表現があります。
詩人が自らに、作品の中でこんな言葉を突きつけると、読者としてはその批評の刃が自分に向けられているような、これまでの自分の生き方恥じるような、そんな思いに追い詰められることがあります。
今回の本の題名につながる『ダリアと殺虫剤(わが<脱獄>について)』という詩は245行、16ページに及ぶ長編で、「老い先短く/いま ここに幽閉されているのは なぜだろう」と閉塞感に満ち、擬人化されたダリアと殺虫剤に「ただの一匹の虫として消されるだろう」と結びます。
ただ、なぜか全ての終わりは感じさせないのですね。そこに付けられた毛利さんの写真は、空へ飛び出すような黒いパーカーの男。まさに「脱獄」を感じさせ、詩の閉塞感とは対をなすような「開放感」も感じられる写真で、詩と響き合って、寄り添うようであり、詩に異論を唱えるようでもある不思議な写真です。
毛利さんの写真は50枚以上あり、詩集ですが写真集でもあります。 毛利さんは、西日本新聞に作家の村田喜代子さんが書いているエッセイにつける写真を担当していますが、村田さんの本の装幀のほとんどを手掛けていることもあって、ときにどちらが主か分からないときがあるほど、存在感のある写真を撮っています。
この才能を見抜いた北川さんが毛利さんに声をかけて、北川さんの最新詩集が「詩と写真集」になったというわけです。カバーはやはり写真で構成され、帯には「北川透の詩はますます研ぎ澄まされ装幀家・毛利一枝の写真が浮遊する…」と書かれています。詩人と装幀家という関係性を超えた本ということで、本当に画期的だと思います。
北川さんの仕事場は山口県下関市の関門海峡のほとりにあって、コロナ禍では行き交う船の数が少ないことから時代の変化を感じ取るなど、仕事場と自在な言葉には関連するものがあります。
毛利さんは福岡市に住んでいますが、下関の対岸の門司港などを何時間も歩き回って、ピントや絞りを自由に操ってシャッターを切り続けたということですが、海峡をはさんだ二人の関係性というのも重要な要素なのですね。
著者と装幀家は密着し、理解し合うことでよりよい本ができますが、今回はその枠を超えて、すばらしい「詩と写真集」に行き着いたということです。詩集としても、写真集としてもすばらしい、それが合わさってこれまでにない本になっているということで、是非手に取ってみてはいかがでしょうか。
この記事はいかがでしたか?
リアクションで支援しよう
この記事を書いたひと

山本修司
1962年大分県別府市出身。86年に毎日新聞入社。東京本社社会部長・西部本社編集局長を経て、19年にはオリンピック・パラリンピック室長に就任。22年から西部本社代表、24年から毎日新聞出版・代表取締役社長。