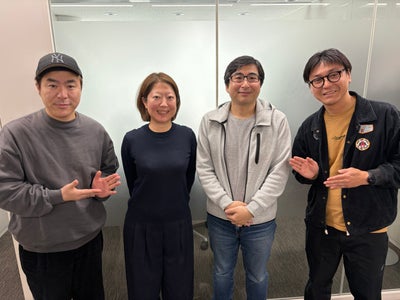2025年も残すところあとわずかとなりました。年末の風物詩といえば、ベートーヴェンの交響曲第9番、いわゆる「第九」がその代表格です。12月19日放送のRKBラジオ『立川生志 金サイト』に出演した、毎日新聞出版社長の山本修司さんが、ベートーヴェンの誕生日を起点に、クラシック音楽と歴史、そして現代社会への想いを語りました。
日本の「第九」初演は福岡に縁があった
12月16日は、ベートーヴェンの255回目の誕生日でした。
年末といえば「第九」ですが、ベートーヴェン自身はこの曲に特別なタイトルを付けていません。日本では「合唱付き」として親しまれ、シラーの詩「歓喜に寄せて」を用いた主題は「歓喜の歌」としてあまりに有名です。
この第九の第4楽章(合唱部分)が日本で初めて演奏されたのは、今から101年前の1924年(大正13年)のことでした。後の昭和天皇となる摂政宮の御成婚を祝うコンサートで、現在の九州大学フィルハーモニーオーケストラの前身である「九州帝国大学フィルハーモニー会」が演奏したと記録されています。福岡は、実は第九と深い縁があるのです。
昭和100年、政治に翻弄された音楽の歴史
今年は戦後80年、そして「昭和100年」にあたる節目の年でもありました。日本の第九の歴史は、まさに激動の昭和とともに歩んできたといえます。
この100年を振り返ると、クラシック音楽を取り巻く環境は時代とともに大きく変化しました。例えば戦時中、日本では敵国語の使用が禁じられ、米英の音楽も放送禁止となりました。しかし、同盟国であったドイツの音楽は許容されていたのです。バッハ、ベートーヴェン、ブラームスの「ドイツ三大B」が戦時中の日本でも聴き継がれたことは、あまり知られていない事実かもしれません。
一方で、音楽は常に政治の影を背負ってきました。名指揮者フルトヴェングラーはナチスへの協力疑いで活動停止処分を受け、現代でもロシアの指揮者ワレリー・ゲルギエフが政治的立場から除名や公演中止に追い込まれています。また、スターリン体制下のソ連では、ショスタコーヴィチが当局の検閲に苦しみながらも、曲の中に密かな「仕掛け」を施して抵抗を試みました。政治が音楽を利用しようとする一方で、音楽家たちはしたたかに表現の自由を守ろうとしたのです。
「有名すぎること」の意外なジレンマ
ところで、あまりに有名な曲ゆえの悩みというのも存在します。 よく聞く話ですが、ある有名な胃腸薬のCMに使われているショパンの「24の前奏曲作品28第7番イ長調」は、イメージが強すぎてピアノ教室の生徒が演奏を尻込みすることがあるそうです。ちなみに、この曲が選ばれたのは「イ長調」が「胃腸(いちょう)」に通じるからだという説もあります。
ベートーヴェンの交響曲第5番「運命」も同様です。「ジャジャジャジャーン」というモチーフは、弟子が「運命が扉を叩く音」と評したことからその名が広まりましたが、あまりに有名すぎて「やりにくい」と感じる奏者もいるようです。実際、1990年代以降のコンサートでは、かつて演奏頻度のトップを占めていたベートーヴェンやモーツァルトの割合が減少し、全体の3割程度になったという分析もあります。
それでも「第九」が人々の心を打つ理由
そんな中でも、「第九」が飽きられることなく日本で定着しているのはなぜでしょうか。それは、プロからアマチュアまで誰もが参加できる機会があり、年末の風物詩として文化に溶け込んでいるからに他なりません。そして何より、その根底にあるメッセージに多くの人が共感しているからでしょう。
今年も世界では戦争が続き、国内でも自然災害や物価高など、心が痛むニュースが絶えませんでした。ベートーヴェンが第九を作曲したとき、彼はすでに聴力のすべてを失っていました。絶望の淵にあってもシラーの詩に感激し、あの大曲を書き上げたのです。
200年近く経っても色褪せない「歓喜」の主題を胸に、明るい新年を迎えたいものです。
この記事はいかがでしたか?
リアクションで支援しよう
この記事を書いたひと

山本修司
1962年大分県別府市出身。86年に毎日新聞入社。東京本社社会部長・西部本社編集局長を経て、19年にはオリンピック・パラリンピック室長に就任。22年から西部本社代表、24年から毎日新聞出版・代表取締役社長。