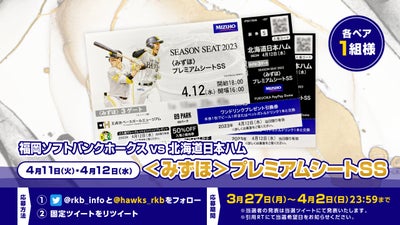福岡と信州をつなぐ大きな結び目のひとつ“安曇族”のことを題材に取り入れた小説です<松本猛・菊池恩恵共著 講談社刊 1800円>。著者の一人、松川村にある「ちひろ美術館」の館長で、いわさきちひろさんの息子さん松本猛(まつもとたけし)さんにお会いすることができました。


福岡と信州をつなぐ大きな結び目のひとつ“安曇族”のことを題材に取り入れた小説です<松本猛・菊池恩恵共著 講談社刊 1800円>。著者の一人、松川村にある「ちひろ美術館」の館長で、いわさきちひろさんの息子さん松本猛(まつもとたけし)さんにお会いすることができました。


さて、この八面大王→八女大君(やめのおおきみ)の読み替えともとれませんか?八女大君というのは、527~8年“磐井の乱”で1年に及ぶ戦いの末、大和朝廷に滅ぼされた(ということになっている)筑紫君磐井のこと。日本書紀では“新羅から賄賂を贈られ、大和朝廷の朝鮮への派兵を邪魔した”ことで討たれた…となっていますが、どうやら、強大化する九州王権を抑えるとともに朝鮮半島とのつながりも支配したかった大和朝廷が仕掛けた戦だったとの説もあります。このころ、玄界灘から対馬海峡を経て朝鮮半島までの制海権を持っていたのは、安曇・宗像・住吉といった海人族。その中でも、安曇族は筑紫君磐井と深くつながっていたようです。磐井の乱の後、磐井の本拠地八女にいなかったので斬殺を免れた磐井の子・葛子は、糟屋の屯倉(みやけ)を大和に差し出すことで命を永らえたのですが、この糟屋地区は安曇族の本拠地なのです。なお、筑後国風土記では「磐井は豊前方面へ逃れ山中で死んだが、大和はその姿を見失った」となっています。福岡で居場所のなくなった磐井の一族が、安曇族とともに日本海を北上する運命になったと考えられますよね。なお安曇野地域は、646年、安曇郡として制定されています。地名になるくらいですから、安曇野に定住した安曇族は、郡になる時点でかなり大きな勢力だったはずですね。古代は文書で残されていないことも多いゆえ、解釈もいろいろ。ロマンが広がるってもんです。小説「失われた弥勒の手」の大きなヒントになったという、 坂本博さん著の「信濃安曇族の謎を追う-どこから来てどこへ消えたか-」(近代文芸社刊・1200円)も、ぜひどうぞ。観光で訪れるのはもちろんですが、古代のロマンをテーマに信州を旅するのはいかがですか?

テキストが入ります。
ここで、松本さんに教えてもらった北部九州と信州の共通点、海の民の名残をいくつか並べてみます。
・ 馬肉を食べる風習も九州と信州。
・ とうがらしのことを“こしょう”と呼ぶ。
・ 魚が大好き。(ただし信州では、基本は全て塩漬けですが)
・ おきゅうと(エゴ・イゴ)を食べる。お盆には必ず食べます。先祖への思いを馳せているのでは?(長野県内でも、梓川以南は食べません)
・ お祭りに出る山車は「ふね」の形。
・ 有明山の存在。有明山があるのは、日本に4ヶ所。安曇野(長野)、善光寺平(長野)、対馬(長崎)、大雪山(北海道)。前3つについては、いずれも神様の降りるきれいな形で、一民族の信仰の対象として見ることができる。ちなみに、信州の有明山には古墳あり。
・ 日本海側にある「有明」という地名は「しか・しが(志賀)」「あづみ(安曇・安住)」とつながっている。
・ 伽耶国(古代朝鮮半島)の影響を受けた古墳・カメ棺・装飾品の出土。
あ、芸術を満喫するのもいいですよ。ということで、ちひろ美術館の外観と庭をおまけにどうぞ。


この記事はいかがでしたか?
リアクションで支援しよう