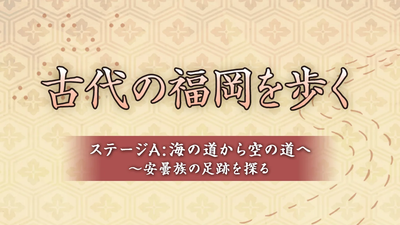ジャニー喜多川氏の少年たちへの性加害を認めた、ジャニーズ事務所の会見が9月7日開かれた。翌8日、RKBラジオ『立川生志 金サイト』に出演した、元サンデー毎日編集長・潟永秀一郎さんが改めて「メディアはなぜ、この問題を報じてこなかったのか」についてコメントした。
社会部記者には縁遠い“芸能界の話”
予めお断りすると、今回の話は、あくまで私に見えていた世界です。それはおそらく、長く芸能界と接点がある方々や、同じメディアでも、テレビのキー局や広告代理店などの方々が見えるものとは違う、メディアの端っこの、一記者の視点で、浅はかかもしれません。あくまで私の視点、個人史としてお話しします。
週刊文春がこの問題をキャンペーン報道した1999年当時、私は毎日新聞福岡総局(現・福岡本部)の記者でした。仕事柄、新聞各紙は毎日必ず目を通していましたが、週刊誌は正直、見出しを斜め読みする程度で、このキャンペーン記事もきちんとは読んでいませんでした。
全国紙で芸能関係の取材をするのは、学芸部や文化部と呼ばれる部署で、社会部だった私は取材対象でなかったことも理由の一つです。これは東京本社も同じで、事件や裁判になって初めて、社会部が取材します。ですから、ジャニーズ事務所が文春を名誉棄損で訴え、ジャニー氏の性加害に関して1審では事務所側が勝訴、2審で文春側が逆転勝訴したことは新聞記事で知っていました。
今回「あの時、メディアがきちんと報じなかったことが問題をここまで大きくした」という指摘があって、それはその通りだと思うのですが、すみません、当時の私には「世界の犯罪史上に残る多数の少年への性犯罪」という認識はありませんでした。
それはなぜだったんだろう、と改めて考えてみて、思い当たるのは「芸能界を別世界だと思っていたこと」です。戦後、興業の世界には反社会勢力との付き合いがあったとか、新人の売り出しやショーレースには大金が動くとか、どれも伝聞で耳にした生半可な知識が「芸能界は多くのタブーがある別世界だ」という認識に置き換わって、その一つと片付けてしまったということです。
また、これは多くの指摘がありますが、2017年に110年ぶりに性犯罪に関する刑法が改正されるまで、法的に強制性交の被害者は女性に限定されていたように、男性の性被害を軽視する風潮に、私も染まっていた面があったでしょう。
週刊誌報道が先行した「ロス疑惑」との違い
ただ、「週刊誌ネタだったから大きく扱わなかったんだろう」という指摘は、私はちょっと違うと感じています。というのも、同じく週刊文春が1984年に報じた「ロス疑惑」は、テレビも新聞も大々的に後追いしたからです。
私は翌85年に毎日新聞に入社しましたが、こちらは自分の持ち場と関係ないのに、毎日ニュースを追っていました。余談ですが、渦中の三浦和義氏が警察に逮捕されたとき、親しい先輩記者が当の三浦氏と一緒にいたという話をのちに聞いて、驚いたことがあります。
それはさておき、私が「ロス疑惑」事件に触れるのは、ジャニーズ問題を考えるうえで二つのポイントがあるからです。
一つは、捜査当局が動くかどうか。さっき言った通り、ロス疑惑では警察が動きました。85年9月、警視庁が三浦氏を妻の殺人未遂罪で逮捕し、のちに有罪が確定しました。これは反省を込めて言いますが、社会部記者は警察や検察が動く「事件」には過剰に反応します。「抜いた、抜かれた」の特ダネ競争になるからです。
決して当局に責任転嫁するつもりはありませんが、もしジャニーズ問題もあの裁判の後、警察が強制わいせつなどで捜査に動いていたら、社会部は学芸部を押しのけて取材に走っていたでしょう。「捜査当局が動かなくても、犯罪は犯罪だろう」というお叱りを覚悟の上で、これが一つ目の現実です。
もう一つは、訴訟への恐れです。三浦氏はその後、妻の殺人容疑でも立件されますが、1審の有罪判決が高裁で逆転無罪となり、最高裁で確定しました。三浦氏はこの間、犯人と断定するかのような一連の報道に対して500件近い名誉棄損訴訟を起こし、その多くで勝訴して賠償金も得ました。
ジャニーズ訴訟では最終的に文春側が勝訴していますが、事務所が文春を訴えたとき、話題になった一つが1億円を超える損害賠償請求額の大きさでした。私は、これは他のメディアに対する一種の脅しである「スラップ訴訟」の側面があると思っています。
訴えられた側は、たとえ勝っても、弁護士費用や時間的拘束などで大きな負担を受けます。特にフリーのジャーナリストにとっては厳しく、「ロス疑惑」報道で敗訴が相次いだ後のメディアには余計、このジャニーズ裁判は「触らぬ神に…」的な圧力になったと思います。
週刊誌にとって「売れる表紙」という存在
以上が、新聞記者当時の私の視点で、ここからは週刊誌の編集長になってからの現実です。
いま当時を振り返って、ジャニー氏の性加害問題について、NHKを含む在京キー局や文春以外の雑誌などの「防波堤」になったのは、間違いなくジャニーズ事務所のスターたちです。それは彼らが意図的に守ったということでなく、結果的にそうなったのですが、ここにも二つのポイントがあります。
一つは指摘されている通り、経済的価値です。私は編集長当時、サンデー毎日の表紙にジャニーズ事務所のタレントさんを積極的に載せました。正直に言います。それは「売れる」からです。雑誌の表紙は、書店やコンビニの棚を飾りますから目につきやすく、芸能事務所にとってはタレントさんの宣伝になるので、多くの売り込みがあります。
ただ、ファンの多いタレントや俳優さんは別格で、逆にこちらからお願いすることが多く、ライバル誌にしか登場しなかった、ある俳優さんの事務所には、私が直接交渉に行ったこともあります。
そういう事務所に比べると、ジャニーズ事務所は平等というか上手でした。幹部が、特に人気の高いタレントさんは、各誌にほぼ均等に割り振り、売れっ子ほど忙しい年末でも、正月の特大号用に時間をとってくれました。
今思えば、事務所側には、それでジャニー氏の問題などに切り込ませないという意図があったのかもしれませんが、そもそも「サンデー毎日」は芸能系のゴシップを書くことはほとんどなく、そういう取材体制も取っていませんでした。だから、ただ「協力的でありがたい」という感覚しかありませんでした。おめでたいと言われればその通りですが、これが正直なところです。
抜け落ちていた取材対象との距離感
もう一つは、タレントさんと知り合った後の、心理的側面です。これは5月のこの番組でもお話ししましたが、インタビューやテレビでご一緒するなどして、個人的に話をする機会が増えると、事務所の暗部を考えることを無意識に避けていたように思います。頭の片隅に性被害のことがあっても、この人をそんな風に見たら失礼だ、という思いです。
会見で井ノ原快彦氏が言った「得体のしれない、触れてはいけない空気」とも少し違う、目の前の人が尊敬の念を込めて面白おかしく語る「ジャニー像」に少し戸惑いながら、むしろ藤島ジュリー景子・前社長が言った「みんなが、そういう事があってスターになったのではない」という言葉を信じるような思いです。
それは今、冷静に考えると、スターを特別視して、被害者を二重に傷つける考え方でもあると気づくんですが、すみません。抜け落ちていたのは、取材対象との距離感を保つ大切さです。少なくとも報道に携わる者は、どの世界であれ、身内意識を持ってはいけないことを、改めて反省します。
以上が、7日の会見を見て、私が痛みとともに振り返ったことです。私はもう現場を離れましたが、後輩たちと会う機会があれば、頭(こうべ)を垂れて話したいと思いますし、今回のことで芸能報道は変わり、タブーはもう許されなくなるのだと思います。
◎潟永秀一郎(がたなが・しゅういちろう)
1961年生まれ。85年に毎日新聞入社。北九州や福岡など福岡県内での記者経験が長く、生活報道部(東京)、長崎支局長などを経てサンデー毎日編集長。取材は事件や災害から、暮らし、芸能など幅広く、テレビ出演多数。毎日新聞の公式キャラクター「なるほドリ」の命名者。
この記事はいかがでしたか?
リアクションで支援しよう