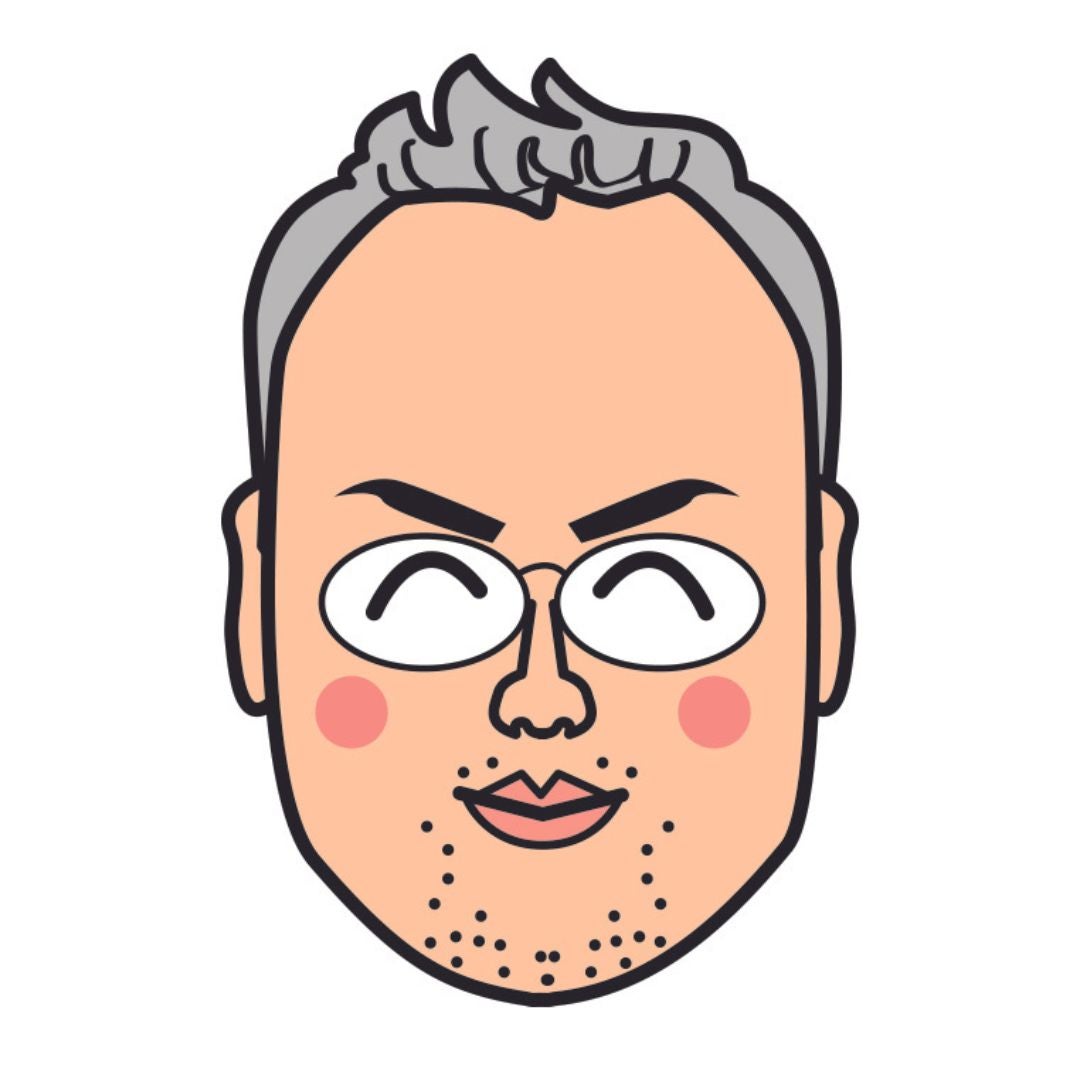世界的な映画祭で受賞を重ねる映画『燃え上がる女性記者たち』を観て、日本の女性記者たちが語るトークイベントが11月12日、福岡市で開かれた。「何のために、記者をするのか」――イベントを取材したRKB毎日放送の神戸金史解説委員長は14日に出演したRKBラジオ『田畑竜介 Grooooow Up』で「改めて原点を感じさせられた」と話した。
「被差別民」「女性」が作った新聞社
『燃え上がる女性記者たち』が、福岡市で上映中です。インド北部で女性たちが2002年に立ち上げた新聞社「カバル・ラハリヤ」を舞台にした長編ドキュメンタリー映画です。
偏見や暴力にひるむことなく、独自のニュースを伝え続ける女性を撮影した作品で、世界各地の映画祭で上映され、いろいろな映画賞を受賞しています。
%20Black%20Ticket%20Films.jpg)
取材する女性記者=(c) Black Ticket Films
主人公たちは、ヒンズー教社会に根深く残るカースト制度(身分制度)の被差別民「ダリト」という階級の方々です。暴力を受けて抗議すると「その階級で何を言うのか」とさらに暴力を受けたり、女性であることで二重の差別を受けたりするなかで、社会の理不尽を報道していきます。
%20Black%20Ticket%20Films.jpg)
取材ではスマートフォンで動画を撮影=(c) Black Ticket Films
- 原題は『writing with fire』。社名の「カバル・ラハリヤ」は「ニュースの波」という意味。映画の冒頭で、主人公は「ジャーナリズムは民主主義の源だと思う」「人権を守る力があるからには、それを人々の役に立てるべきだと思う」「でなきゃ、メディアも他の企業と同じ、単なるお金もうけになってしまう」と語る。
「就職できない」と冷笑したネット民もいた
この映画の上映に合わせて11月12日(日)、九州の女性記者たち3人に話を聞こうというトークイベントが開かれました。
そのうちの1人、熊川果穂さんは熊本日日新聞の記者です。警察・司法を担当した後、今は新聞の紙面を作る部署に勤務しています。私は熊川さんのことを学生時代から知っていて「30歳になりました」と言われてびっくりしてしまいました。
発言する熊日新聞の熊川果穂記者
熊川果穂記者:2015年に、安倍政権の時に安保法制が強行採決されたっていうことで、学生で「福岡ユースムーブメント」というグループを作って、天神のパルコ前や警固公園周辺でデモをしたり、学生たちで警察署に許可を取りに行ったりして活動していました。やっぱり「就職が難しい」とか聞きながら就活をしていたんですけど、「ちょっとやばい奴が入ってきた」みたいな噂は一部の先輩にあって、ただ働いている中では特に言われることもなく、1人の警察官から「あいつはやばい奴、という通知は上から来たけど、俺は君を1人の人間として見ているから、自分で話してどういう人間かを知りたかった」という話を懇親会の席で言ってくださったのが今も心に残っていて、「やってきたことで決め付けない人も、権力側、警察の中にもいるんだな」と感じたりしました。
活動的な学生さんで、就職のこと、ネット上でやゆされたりしたのを見ていましたが、立派にちゃんと就職して、働いています。
では、こういう権力批判をすると「左翼がかっている」のか。よく言われるのですが、僕らはそう思っていません。例えば中国やロシアで政権批判すれば今度は「右翼」と言われますよね。左翼とか右翼とか、時の政権が罵倒する時に使う言葉です。
権力の側に対して逆の側に立ってきちんとチェックをしたり、弱い人の側に立ってものを見たりするというのは、とても重要な記者の資質です。「いい記者になったな」と思います。
インドでは2014年以降、40人の記者が殺されているのだそうです。厳しい時代、社会に生きる記者はそういう状態に置かれています。日本も戦前はまさにそういう状態でした。
映画の中では、女性記者は「ダリト」という差別される側なので、教育を受ける機会がなく、読み書きが苦手で四苦八苦している若い記者も出てきます。こういう人たちが報道を続けていくことの意味を、映画は語っています。
歴史の目を持って「文化で戦う」
2人目、毎日新聞の上村里花さんはベテランです。いわゆる報道、政治部や社会部と違う、文化を担当する学芸記者をしていて、その役割をこう語っています。
毎日新聞の上村里花記者
上村記者:「文化を軽視する国に未来はない」と思っていまして、文化部からやれることはたくさんある。社会部や政治部は日々の動きをキャッチすることが第一になりますので、とにかく「来る球をキャッチして投げ返す」という動きになります。一方、文化部は、どんどん深掘りしていくわけです。今日あった事象だけを書くんじゃなくて、過去にまで遡って、視点を持って、歴史の目を持って書いていくのが文化部の仕事ですので、そこからやれることは非常に大きいと思うんですね。
何年にもわたって一つのテーマを掘り下げて連載するのは、文化部でないとなかなかできないと思います。例えば水俣というのは非常に重要なテーマで、終わっていないだけじゃなくて、まさに私達の問題なんですね。「まだ患者さん苦しんでいる方がいるから」「訴訟が終わってないから」という捉え方をされるかもしれませんけども、それだけじゃなくて、水俣で起こったことが今まさに福島でも起こり、今の日本社会で起こっている。「私達は水俣に学ばなかったのか」「広島・長崎に学ばなかったのか」。そういうことが今の社会に起こっていて、それは全部私達に跳ね返っているんですね。そういうものを、歴史の目を持ってきちんと忘れないように伝えていく、自分の視点を持って伝えていくことは、非常に今の社会、自分たちの問題を考える上でも重要で、文化部の戦い方はそういうところじゃないかなと思っています。
確かに「いろいろな戦い方はある」と、話を聞きながら思っていました。
日本のメディアは「後れを取っている業界」
ただ、女性ならではの負担にも直面しています。3人目、西日本新聞の黒田加那記者は、ネットメディアの担当をしています。会場には来春から放送局の記者に内定している大学生も来ていて、質問が出ました。
質問する大学生
学生:夫が無理解であったりとか、結婚を迫られて途中で辞めてしまうみたいな記者さんが出てきたかなと思うんですけれども、私も将来的に不安視しているところも若干あって、そうしたところでの壁だったり、難しさであったり、両立されていてお考えのことがあればお聞きしたいです。
黒田加那記者:2歳半の息子が1人おります。産休・育休を経まして、2022年度から復職して働いているんですけれど、特に結婚・妊娠・出産とキャリアは「トレード・オフ関係」にあるかのように、女性はどうしても感じてしまう現状がありまして、やっぱりメディア、新聞社の中にも感じるところがあって。私の場合、幸いに夫はとても理解があり、家事と育児もすごく参加してくれますし、割合でも多分、夫と私で6対4ぐらいで夫が多く負担してくれているんじゃないかなと思うんですけれども、今まで入社して結婚するまでと同じ働き方はどうしてもできなくなってしまうんですね。
新聞社の考える「記者のスタンダードタイプ」がちょっとオールドタイプというか、具体的に言うと高度経済成長期のサラリーマン的な、企業戦士ではないんですけれども、専業主婦の奥さんがいて家のことをやってくれる替わりに、仕事に全力投球できるみたいな形がいまだにスタンダードになってしまっているんじゃないかな。社内の仕組みだったり、仕事のやり方もそういうのがベースになっているので、どうしてもそこに合わせられない人は離職してしまう人もいますし、「編集の仕事をしたかったけれど、やっぱり編集じゃない仕事の方が融通が利くから、そっちに行かないといけない」とか、変えざるを得ない方もいます。私が入社した当時からしても、今はかなり女性を支えるような制度や仕組みはだんだん整ってきてはいるんですけれども、ではメディアがライフ・ワーク・バランスを支えていくような環境にできているかと言うと、「後れを取っている業界」なんじゃないかなと、私は個人的には思っています。
西日本新聞の黒田加那記者
私は男性ですが、女性記者が「半分」ではなく、「半分以上」になった方がいいのではないか、とずっと思っています。多様性も出てくるし。もちろん大切な仕事を背伸びしてでもやらなきゃいけない時はありますが、日ごろのことをきちんとするためにはいろいろな視点が入った方がいいな、と思っています。
「カバル・ラハリヤ」の再生回数は1億5000万回、登録者は30万人を超えたそうです。メディアとして生き残っていくためには、いろいろな挑戦が必要なのではないでしょうか。
映画『燃え上がる女性記者たち』は、福岡市中央区天神のKBCシネマで上映中です。佐賀市のシアターシエマでは12月15日から上映されます。
この記事はいかがでしたか?
リアクションで支援しよう
この記事を書いたひと
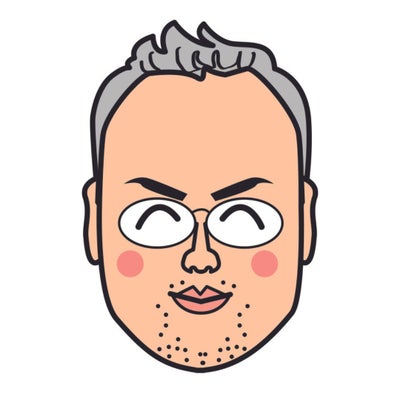
神戸金史
報道局解説委員長
1967年、群馬県生まれ。毎日新聞に入社直後、雲仙噴火災害に遭遇。福岡、東京の社会部で勤務した後、2005年にRKBに転職。東京報道部時代に「やまゆり園」障害者殺傷事件を取材してラジオドキュメンタリー『SCRATCH 差別と平成』やテレビ『イントレランスの時代』を制作した。現在、報道局で解説委員長。