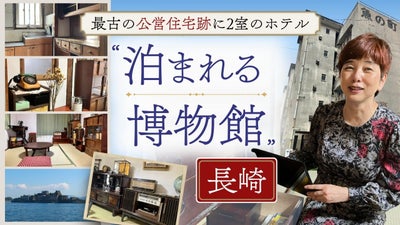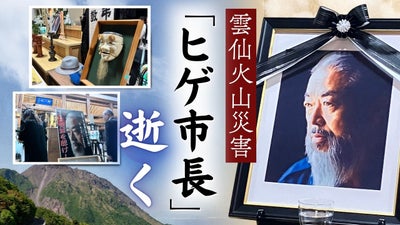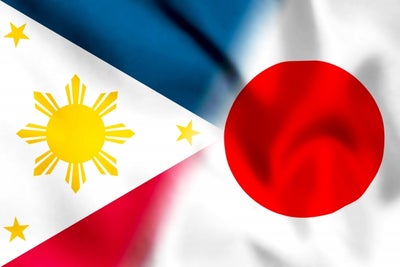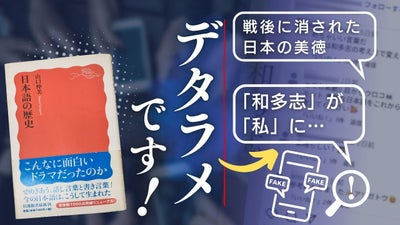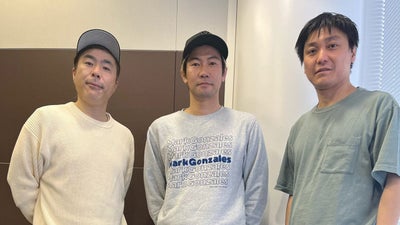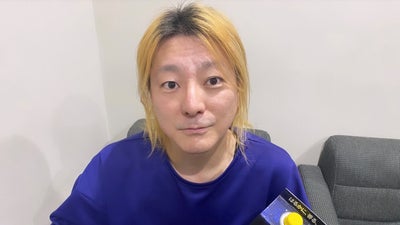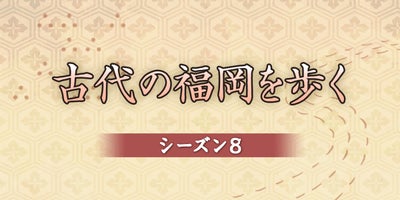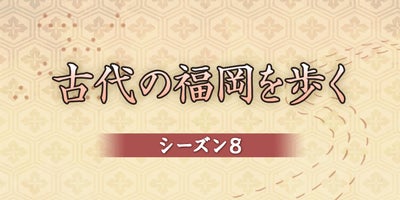目次
性的マイノリティ(LGBTQ+)の人たちの活動を支持し、支援している人たちのことを、ストレートアライ(Straight Ally)、短く「アライ」と呼ぶ。アライの一人、神戸金史RKB解説委員は、3年ぶりのリアル開催となった「九州レインボープライド2022」のパレードに参加し、RKBラジオ『田畑竜介 Grooooow Up』で報告した。
カラフルな虹色に思いを乗せて
「九州レインボープライド2022」が11月6日(日)、博多区の冷泉公園で開かれました。性的マイノリティの人たちを尊重していこうという運動を、社会に広めていきたい人たちが集まります。会場もパレードもレインボーフラッグで虹色に染まっていて、非常に楽しい感じでした。
ステージではアーティストのライブやトーククッションもありましたし、いろいろな企業がブースを出しています。日本航空、ライフネット生命、地元の三好不動産、ドン・キホーテの福岡のお店、博多マルイ。団体だと車いすラグビーチーム「Fukuoka DANDELION」など。主催者発表で、来場者は約1万5000人ということです。2015年から始まったんですが、この2年間はオンラインイベントだったので、リアル開催は3年ぶりということで、にぎわいました。
ステージではアーティストのライブやトーククッションもありましたし、いろいろな企業がブースを出しています。日本航空、ライフネット生命、地元の三好不動産、ドン・キホーテの福岡のお店、博多マルイ。団体だと車いすラグビーチーム「Fukuoka DANDELION」など。主催者発表で、来場者は約1万5000人ということです。2015年から始まったんですが、この2年間はオンラインイベントだったので、リアル開催は3年ぶりということで、にぎわいました。
スタジオに持ってきたこのレインボーフラッグは会場で買いました。今かぶっている自前の帽子は花柄ですが「こういう日はいいかな」と。靴下の色は右を赤に、左を青にして、その格好のまま地下鉄に乗って会場に行きました。会場で会った知り合いの弁護士さんは、七色の長髪のかつらをかぶっていました。
神戸:すごいカツラですね。
後藤富和弁護士:ははは。これ、けっこう似合ってるでしょ。僕は気に入っているんです。福岡県弁護士会として、参加しています。
神戸:会として応援しようと?
後藤弁護士:全ての人の人権を保障するということなので、当然のことですね。(レインボープライドは)規模、大きいですね。多分、福岡でのデモとしては最大じゃないですかね。見てわかるように、若い世代が多いなっていう印象を持ちますね。
神戸:(近くにいた少年を見て)若い世代ですね!
中学生:『カリメン』に出させていただきました。
神戸:えっ? RKBラジオの『カリメン』に出てもらったの? ありがとうございます!
※RKBラジオの若者向け番組『カリメン』
https://rkb.jp/radio/kari/
若い世代に広がる共感
この集会自体が、「LGBTQ当事者を筆頭に、世の中の差別や偏見から子どもたちを守り、子どもたちが前向きに自分らしく生きていくことができる社会の実現を目指しています」といううたい文句。この中学生は理不尽な校則に反発していて「学校の中での男女の名前の順番がきれいに分かれているのもおかしい」と話していました。
中学生:自分らしく生きていけたらいいと思いますし、そういう社会になれるように、まずは行政や国に頑張ってもらう。そこから広がっていくと思いますし、1人1人が声を上げることが大事なのかなと思っています。
会場は若い人がとっても多かったです。性的マイノリティは若い人たちの支持を受けているな、という感じがしました。
中学生:自分らしく生きていけたらいいと思いますし、そういう社会になれるように、まずは行政や国に頑張ってもらう。そこから広がっていくと思いますし、1人1人が声を上げることが大事なのかなと思っています。
「LGBTQ+」とは?
「LGBT」は、セクシャルマイノリティの総称。「レズビアン」(L)は女性の同性愛者。「ゲイ」(G)は男性の同性愛者。それから「バイセクシャル」(B)は両性愛者。ここまでが「愛する対象が、誰か」という話です。それとは別に、「自分はどういう人間なのか」というのが、性自認。「トランスジェンダー」(T)は出生時の性と違う性で生きようとしている人たち。性同一性障害も含みます。
また、まだまだ自分のことがよくわからないという「クエスチョニング」(Q)と言われる人たちもいます。自分がどちらの性なのか意図的に決めていないと言う人も。自分の内心ですね。そこまで合わせて「LGBTQ」。そして今は、どれにも当てはまらないという方もいらっしゃるので、「+(プラス)」をつけることが多いです。「LGBTQ+」という言い方、覚えておいてください。
また、まだまだ自分のことがよくわからないという「クエスチョニング」(Q)と言われる人たちもいます。自分がどちらの性なのか意図的に決めていないと言う人も。自分の内心ですね。そこまで合わせて「LGBTQ」。そして今は、どれにも当てはまらないという方もいらっしゃるので、「+(プラス)」をつけることが多いです。「LGBTQ+」という言い方、覚えておいてください。
「女性と結婚したら、縁を切る」と母に言われた娘
そして、パレードが始まりました。ブラスバンドがついて800人くらい。人数制限をしていて5つの隊列にわかれ、私も、このレインボーフラッグを振りながら歩きました。冷泉公園からアクロス福岡、天神南駅、川端商店街を回って戻ってくる約3キロ、たまたま隣を歩いていた女性がいたので、話を聞いてみました。
バイセクシャルのオリコさん(28歳):(母親に)「自分はこういうセクシャリティで、将来家族となる相手が女性になるかもしれない」という話をしました。
神戸:そしたらどうなったの?
オリコさん:そしたら、「やっぱりちょっと、今受け入れられない。実際連れてきたら縁を切るよ」とその時は言われました。
神戸:それは、常識から離れられないということなのかな?
オリコさん:そうですね……でも、親も知らないというか、身近にある世界だと思ってないからだと思うので、今もずっとめげずに話をして、だんだん受け入れてきてくれてるんじゃないかなと思います。
神戸:うまくいったらいいですね。
オリコさん:そうですね(笑)
福岡市のオリコさん(28歳)は、バイセクシャル、男女を問わず愛することができるので、「女性と結婚することだってありうるかもしれない」と母親に伝えたところ、「縁を切る」と言われたそうです。動揺しつつも娘のことを考え、認めるという人が多いのかな、と私は思っていたんですが「縁を切ると言われた」と聞いて、びっくりしました。「自分はどうなるか将来わからないんだけど、そういう人たちがいることを知ってほしい」とオリコさんは話していました。
バイセクシャルのオリコさん(28歳):(母親に)「自分はこういうセクシャリティで、将来家族となる相手が女性になるかもしれない」という話をしました。
神戸:そしたらどうなったの?
オリコさん:そしたら、「やっぱりちょっと、今受け入れられない。実際連れてきたら縁を切るよ」とその時は言われました。
神戸:それは、常識から離れられないということなのかな?
オリコさん:そうですね……でも、親も知らないというか、身近にある世界だと思ってないからだと思うので、今もずっとめげずに話をして、だんだん受け入れてきてくれてるんじゃないかなと思います。
神戸:うまくいったらいいですね。
オリコさん:そうですね(笑)
「私の周りから社会を変えていけたら」と高校生
パレードで歩いていたら、横に「高校生かな?」と思う人がいたんです。聞いたら、福工大城東高校のダンス部の生徒でした。ダンス部は、会場のステージで踊っていたんです。顧問の先生をとても尊敬していて「先生から聞いて、部として参加することにしたんです」と話してくれました。ステージに出た後は、パレードの沿道警備ボランティアとして一緒に歩いていました。うれしくなって、さらに話を聞いてみました。
松尾瑞葵さん:大人の中に混じって話を聞くのって、本当に貴重だなって思いました。もうすぐ大人になるから、なんかやっぱ大人の意見を聞いて、そうだなと思ったら自分にもいっぱい取り入れていきたいなって思うし。
神戸:元々、自分の中に偏見がありましたか?
松尾さん:私は、なかったですね。別に否定はしないけどその問題を解決するために何か行動をしたことがなくて。でも先生からお話をいただいて、「自分もこういう啓発活動をしたい!」という気持ちから参加させていただきました。そういう(性的マイノリティの)方たちが「否定される世の中の方がおかしいんじゃないか」って、今日来てやっぱり改めて感じました。私の周りから、「そういう活動してる人がいるよ」と考え方を変える、自分で柔軟に変えていくのはすごい大事なことだと思うので。あとは私の周りの小さいことから少しずつ変えて、そこから大きく社会が変わっていけたらなって思って。
福工大城東高校の松尾瑞葵さん(17歳)は「自分の周りから変えて、社会が変わっていったらいいな」と話してくれました。ラジオを聴いている方には、同性愛と聞くと一歩引いちゃう方もいるかなと思うんです。だけど、若い世代の間では本当に抵抗がなくなっています。1人1人が伸びやかに暮らしていく社会の方がいいと思っている人が増えています。
松尾瑞葵さん:大人の中に混じって話を聞くのって、本当に貴重だなって思いました。もうすぐ大人になるから、なんかやっぱ大人の意見を聞いて、そうだなと思ったら自分にもいっぱい取り入れていきたいなって思うし。
神戸:元々、自分の中に偏見がありましたか?
松尾さん:私は、なかったですね。別に否定はしないけどその問題を解決するために何か行動をしたことがなくて。でも先生からお話をいただいて、「自分もこういう啓発活動をしたい!」という気持ちから参加させていただきました。そういう(性的マイノリティの)方たちが「否定される世の中の方がおかしいんじゃないか」って、今日来てやっぱり改めて感じました。私の周りから、「そういう活動してる人がいるよ」と考え方を変える、自分で柔軟に変えていくのはすごい大事なことだと思うので。あとは私の周りの小さいことから少しずつ変えて、そこから大きく社会が変わっていけたらなって思って。
広がるパートナーシップ宣誓制度
福岡市役所も会場でパートナーシップ宣誓制度のパンフレットを配っていました。今は同性同士の結婚は認められていませんが、パートナーだと宣誓して行政が認定することによって、その証明を持って行くと、例えば民間のサービスで、携帯電話の家族割とかマイレージの共有、銀行でのペアローンとか、そういったサービスが受けられるように、民間もどんどん変わり始めています。結婚制度が変わっていない以上、行政の方でも何らかの対応をしたいという動きが始まっているということです。
「同性婚を認めると、ただでさえ少ない子供がもっと産まれなくなる」と言う方がまだいらっしゃるんですけど、全体からしたらマイノリティなので、人口とは全く関係ありません。選択的夫婦別姓も同性婚も、認めても誰も困らない。僕らマジョリティは何も関係ないわけです。
変えたくない人はそのままでよくて「現状で困っている人が幸せに生きられるように、変えましょう」というだけなので、他の人が出てきて「同性婚はダメだ」「選択的夫婦別姓もダメ」と言うのはどうなのかなと思います。多くの人が伸びやかに生きられるように、とオリコさんや松尾瑞葵さんが話していました。そんな社会に早くなったらいいという気持ちを込めて、これから毎年、レインボーフラッグを振りに行こうと思っています。
神戸金史(かんべかねぶみ) 1967年生まれ。毎日新聞に入社直後、雲仙噴火災害に遭遇。福岡、東京の社会部で勤務した後、2005年にRKB毎日放送に転職。東京報道部時代に「やまゆり園」障害者殺傷事件を取材して、ラジオ『SCRATCH 差別と平成』(放送文化基金賞最優秀賞)やテレビ『イントレランスの時代』(JNNネットワーク大賞)などのドキュメンタリーを制作した。
「同性婚を認めると、ただでさえ少ない子供がもっと産まれなくなる」と言う方がまだいらっしゃるんですけど、全体からしたらマイノリティなので、人口とは全く関係ありません。選択的夫婦別姓も同性婚も、認めても誰も困らない。僕らマジョリティは何も関係ないわけです。
変えたくない人はそのままでよくて「現状で困っている人が幸せに生きられるように、変えましょう」というだけなので、他の人が出てきて「同性婚はダメだ」「選択的夫婦別姓もダメ」と言うのはどうなのかなと思います。多くの人が伸びやかに生きられるように、とオリコさんや松尾瑞葵さんが話していました。そんな社会に早くなったらいいという気持ちを込めて、これから毎年、レインボーフラッグを振りに行こうと思っています。
神戸金史(かんべかねぶみ) 1967年生まれ。毎日新聞に入社直後、雲仙噴火災害に遭遇。福岡、東京の社会部で勤務した後、2005年にRKB毎日放送に転職。東京報道部時代に「やまゆり園」障害者殺傷事件を取材して、ラジオ『SCRATCH 差別と平成』(放送文化基金賞最優秀賞)やテレビ『イントレランスの時代』(JNNネットワーク大賞)などのドキュメンタリーを制作した。
この記事はいかがでしたか?
リアクションで支援しよう