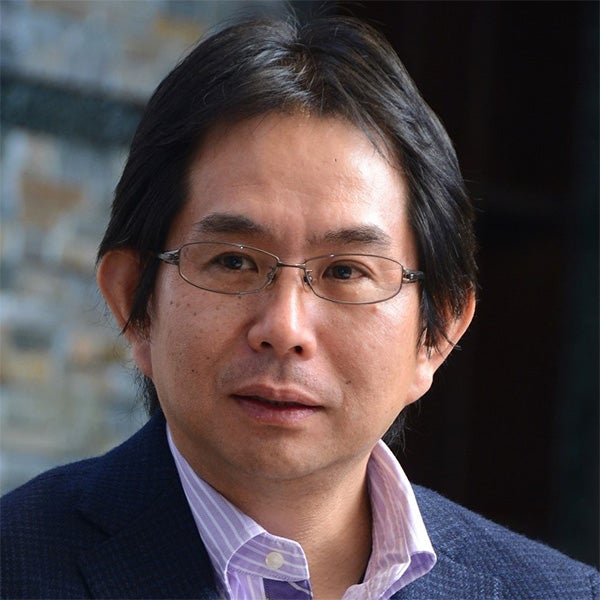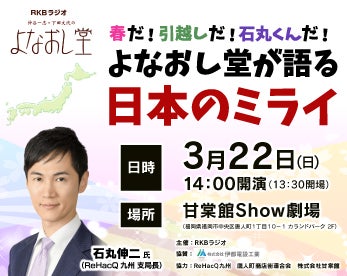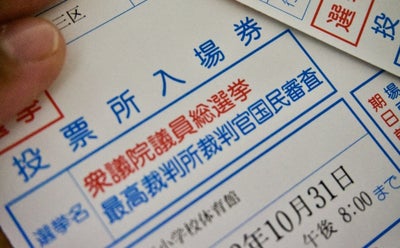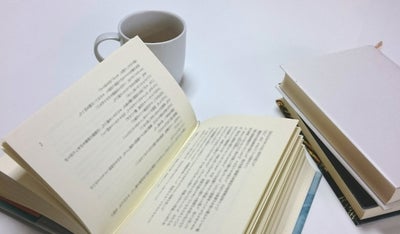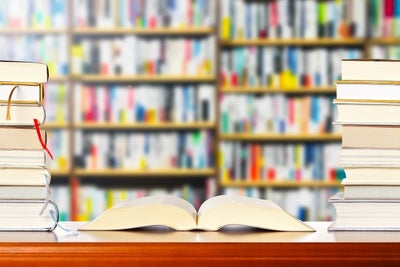鹿児島県警の元幹部が内部情報を漏らしたとして、国家公務員法の守秘義務違反容疑で逮捕された事件が、大きな波紋を広げている。その動機について「県警本部長が警察官の犯罪を隠蔽しようとしたのが、どうしても許せなかった」ことだと明かしたからだ。RKBラジオ『立川生志 金サイト』のコメンテータ・元サンデー毎日編集長の潟永秀一郎さんは6月14日の放送で「単なる情報漏洩事件にとどまらない、深刻な問題をはらんでいる」とコメントした。
ネットニュースメディアに家宅捜索
まず、経緯を振り返ります。発端は去年の10月、福岡市に本社を置くネット上のニュースメディア「ハンター」に、鹿児島県警の内部文書が掲載されたことでした。この流出元として今年4月8日、当時、曽於警察署勤務の藤井光樹巡査長が、地方公務員法の守秘義務違反容疑で逮捕され、同じ日にハンターの中願寺純則代表宅に突然、家宅捜索が入りました。
中願寺代表が弁護士を通じて県警に送った「苦情申し出書」などによると、令状も示されないままパソコンや携帯、書類などを押収し、パソコンは返却の際、一部データを消されたといいます。このパソコンにあったのが、今回の逮捕容疑となった告発文でした。県警はこの送り主を調べ、5月13日に前・生活安全部長の本田尚志・元警視正を逮捕します。
ところが6月5日、鹿児島簡易裁判所で開かれた勾留理由の開示請求手続きで、本田・元警視正が「私がこのような行動をしたのは、鹿児島県警職員が行った犯罪行為を、野川明輝本部長が隠蔽しようとしたことがあり、そのことが、いち警察官としてどうしても許せなかったからです」と意見陳述したことで、情報漏洩ではなく、不正を告発する「公益通報」ではないか、という議論が巻き起こったわけです。
隠蔽事案として本田・元警視正が挙げた事件は二つ。一つは去年12月、鹿児島県枕崎市のトイレで起きた盗撮事件です。容疑者は枕崎署の巡査部長で、意見陳述によると「本部長指揮事件となりましたが、野川本部長は『最後のチャンスをやろう』『泳がせよう』と言って、本部長指揮の印鑑を押さなかった」と訴えました。もう一つは、現職警察官が「巡回連絡簿を悪用した」ストーカー事案です。「この件についても、県民の皆様に公開し、説明すべきだと思いましたが、明らかにされることはなかった」と言います。
これに対し、野川本部長は「隠ぺいを意図して指示を行ったことは一切ない」と否定したうえで、盗撮事件については5月に巡査部長を逮捕し、ストーカー事件については「被害者の気持ちを踏まえて2月に捜査を終結し、関係職員を処分した」と説明しています。一方、本田・元警視正は今年5月になって盗撮事件が立件されたのは「私が送った文書がきっかけになったと思う」と陳述しています。
「取材源の秘匿」尊重してきた捜査機関が一線を超える
ではここから、二つの情報漏洩事件から浮かび上がった問題についてお話しします。
第一は、その捜査手法。「報道の自由」の侵害です。先ほど言ったように、鹿児島県警は「ハンター」のニュースサイトに県警の内部文書が掲載された情報漏洩容疑の関係先として代表の自宅に家宅捜索に入り、取材資料などを押収しました。
それは文書を漏洩したとされる巡査長の容疑の裏付けにとどまらず、パソコンのデータから別の告発文を見つけて、本田・元警視正の逮捕に至る捜査の端緒にもなりました。本田・元警視正が札幌市在住のジャーナリスト・小笠原淳さんに送った手紙の画像データが、ハンターのパソコンに残っていたからです。
ご存じの通り、報道機関にとって「取材源の秘匿」は「いかなる犠牲を払っても守るべきジャーナリズムの鉄則」で、日本新聞協会と日本民間放送連盟はその旨を発した2006年の声明で「隠された事実・真実は、記者と情報提供者との間に『取材源を明らかにしない』という信頼関係があって初めてもたらされる。その約束を記者の側から破るのは、情報提供の道を自ら閉ざし、勇気と良識をもつ情報提供者を見殺しにすることにほかならないからである」と表明しています。憲法が保障する「報道の自由」の根幹の一つで、捜査機関も最大限尊重し、慎重に対応してきました。日本は民主主義国家だからです。
ところが今回、ハンターの中願寺代表も小笠原氏も一切の捜査協力を拒む中、鹿児島県警は家宅捜索で押収した資料から、捜索容疑以外の取材源まで洗い出し、本田・元警視正を逮捕しました。強制捜査でネタ元を突き止める――明らかに一線を超えたやり方で、こんなことが許されたら、日本は報道の自由が担保されない国になります。
大げさと言われるかもしれませんが、少なくとも鹿児島県警職員には「同じことをしたらこうなる」という脅し、見せしめになったでしょうし、ハンターはほかにも鹿児島県警関係者の事件もみ消し疑惑などを報じていますから、今後の報道つぶし、ネタ元つぶしの意図も感じる強制捜査です。
「捜査資料の廃棄」を促す文書データを消去
また、押収したパソコンからデータを消した、というのも凄い話ですよね。ハンター側から県警への「苦情申し出書」によると、パソコンを返す際、保存していた「刑事企画課だより」という文書データを、中願寺代表が拒んだにもかかわらず捜査員が消去したといいます。「内部文書ですから」と言ったそうですが、この文書の中身こそが2番目の問題。「捜査資料の廃棄」を促す内容なんです。
去年10月2日付の「刑事企画課だより」で、ハンターが11月に、実物の写真と共に報じました。「捜査資料の管理について」と題し、「最近の再審請求等において、裁判所から警察に対する関係書類の提出命令により、送致していなかった書類等が露呈する事例が発生」などと説明し、「再審や国賠請求等において、廃棄せずに保管していた捜査書類やその写しが組織的にプラスになることはありません!」と、びっくりマーク付きで強調し、「未送致書類であっても、不要な書類は適宜廃棄」するよう呼びかける内容でした。まるで再審請求つぶし、いや冤罪の助長にすら取れます。
日本の刑事司法で冤罪を生む土壌の一つは、「証拠の非開示」=捜査段階で警察が収集した証拠を、必ずしもすべて裁判で出すわけではない=ということです。この「隠された証拠」が見つかって再審になった例は複数あり、例えば39年前、熊本県の旧松橋町で男性が刺殺された「松橋事件」では、元受刑者の男性が「燃やした」と自白したはずのシャツ片を検察が持っていたことが分かり、再審開始とその後の無罪につながりました。
また40年前、滋賀県日野町で起きた強盗殺人事件は、第2次再審請求で初めて開示された証拠の中に、自白の信用性に強い疑いを生じさせる写真のネガがあり、地裁と高裁で再審開始の決定が出ました(検察側が最高裁に特別抗告)。どちらも最初からすべての証拠が裁判所に出ていれば、無罪の可能性が高かった事件です。
そんな証拠保全の重要性を「組織的にプラスになることはない!」と断じて廃棄を促す文書が明るみに出て、おそらくは警察庁からも報告を求められたのでしょう、県警は表現を一部書き換えて出し直さざるを得なくなりました。今回、家宅捜索の後で捜査員が消したとされるのは、元の文書の画像のようですが、既に世間に流布され、国家公安委員長も記者会見で存在を認めたものを消してどうなるのか。捜査員に消す権限はないはずで、腹いせとも取れますし、ある意味、県警の隠蔽体質を露呈したともいえる行為です。
えん罪・不祥事が続く鹿児島県警
最後に三つ目の問題点は、そもそも鹿児島県警の不祥事の多さです。過去20年で見ると、えん罪事件が2件。うち1件は有名な「志布志事件」で、2003年の県議会議員選挙で当選した無所属議員の陣営が住民に焼酎や現金を配ったとして、公職選挙法違反容疑で議員本人ら12人を逮捕しましたが、違法な取り調べで自白を強要されたとして全員に無罪判決が出ました。もう1件は2012年、鹿児島市の繁華街で女性に性的暴行をしたとして逮捕した男性に、2審の高裁判決で逆転無罪が言い渡され確定しています。
また、公表されなかった不祥事が少なくとも4件。例えば2020年に警察官3人が捜査書類を偽造したとして書類送検され、処分されましたが、共同通信が報じるまで公表せず、去年10月に南日本新聞が報じ、本田・元警視正も隠蔽を訴えた警察官によるストーカー事件は、県議会で質問されても処分内容すら明らかにしませんでした。
近年は警察官による性犯罪が多発し、本田・元警視正が告発し5月に枕崎署員が逮捕されたトイレ盗撮事件を含め、2020年以降だけで計5件。この中には女子中学生の児童買春や、13歳未満の女児への強制性交も含まれます。
本田・元警視正が意見陳述で指摘したように、不祥事の多発が隠蔽を生むのか、それとも自浄作用が働かない隠蔽体質が不祥事を生むのか、私にはわかりません。
また今回、本田・元警視正が「あった」と訴え、野川本部長は「一切ない」という捜査隠蔽の真相はどうなのか。警察庁は県警による捜査や調査の結果を踏まえ、県警への監察を実施する方針ですが、果たして“身内”の調査がどこまで踏み込めるのか――。むしろ本田・元警視正が起訴されて裁判になった場合、弁護側は「公益通報」を主張するでしょうから、この法廷での争いのほうが、県警の「闇」に迫る気がします。
もちろん、実直で温かい警察官も多数いることは、ここで育ち、記者としても勤務した一人として知っていますが、組織に問題があることはもはや否めないでしょう。これを機に、抜本的な立て直しが求められていますし、それは150万県民に対する責務だと思います。日本の警察の創設者にして、「日本警察の父」とも言われる川路利良大警視は、薩摩藩士でした。先人に恥じない組織の再生を、鹿児島県出身者の一人として、私も願っています。
この記事はいかがでしたか?
リアクションで支援しよう
この記事を書いたひと

潟永秀一郎
1961年生まれ。85年に毎日新聞入社。北九州や福岡など福岡県内での記者経験が長く、生活報道部(東京)、長崎支局長などを経てサンデー毎日編集長。取材は事件や災害から、暮らし、芸能など幅広く、テレビ出演多数。毎日新聞の公式キャラクター「なるほドリ」の命名者。