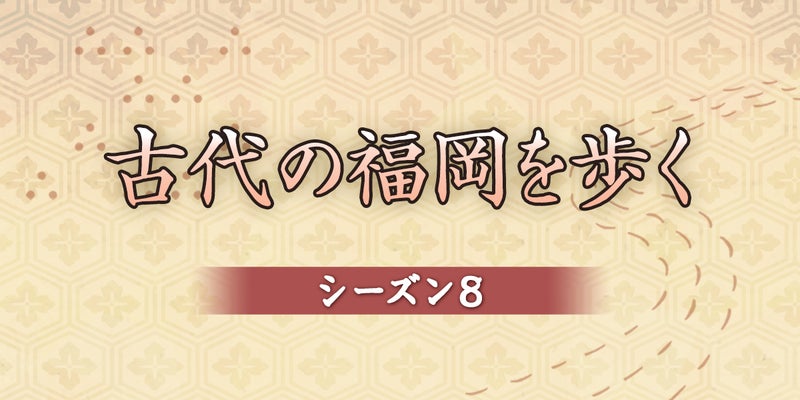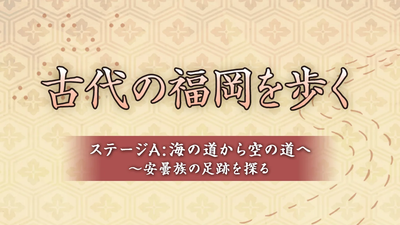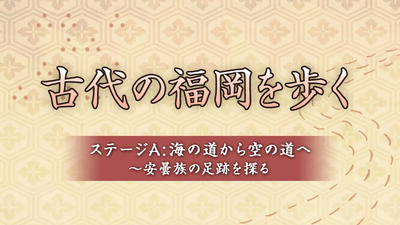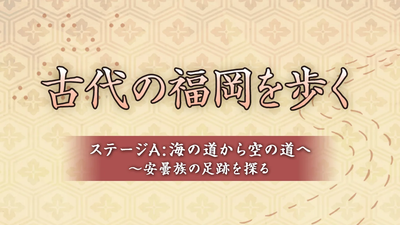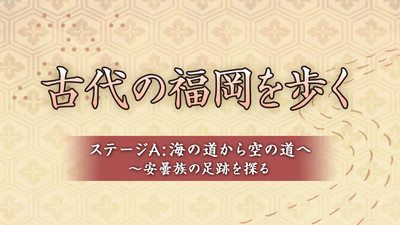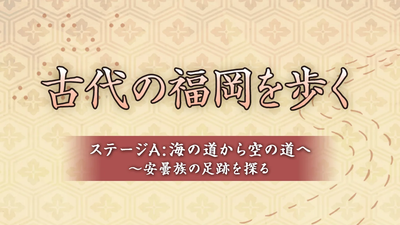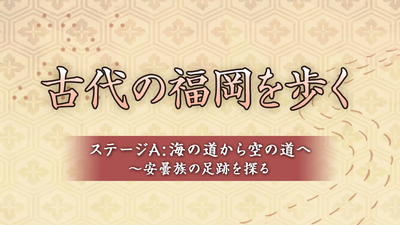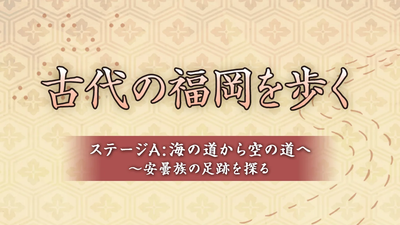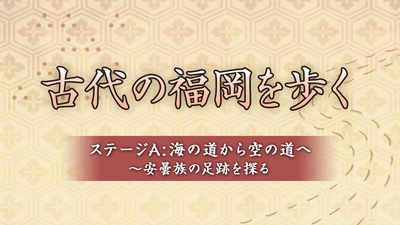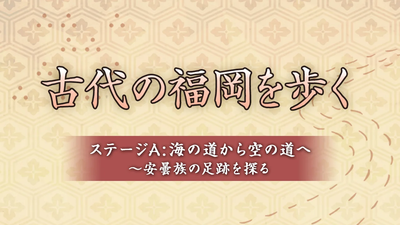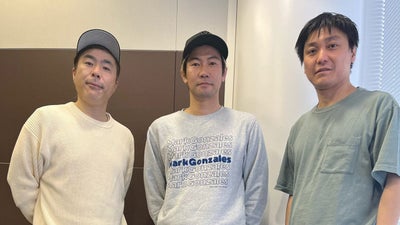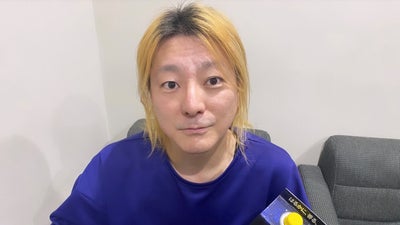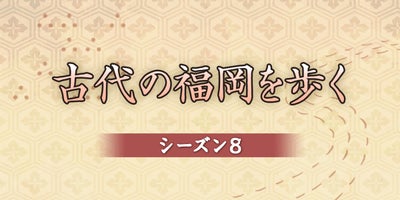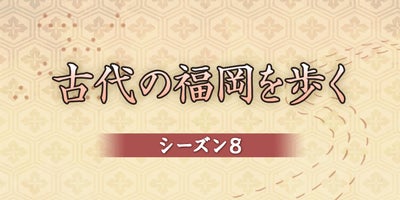この釜跡公園の釜では6世紀後半から須恵器を作り始め、7世紀中頃には瓦も作るようになりました。
ここでは豊前国分寺の屋根瓦を作っています。
その工房跡が復元してあります。工房は縦の長さ30メートル程の吹き抜けの屋根のついた建物が二棟あります。
公園の奥の方、少し高台になったところにあるのが堂がえり釜跡。
ここの釜で豊前国分寺の瓦を焼いたのです。
釜は発掘調査された状態で見学できます。
釜には屋根がつけられ、横に見学用に階段がついたもので、釜の長さが10メートルもあるものです。
下の焚き口に立ち、釜の口からのぞくと、瓦をどうやって焼いたか分かります。 道の駅むなかたでハイレベルに揃えられるお正月準備。
道の駅むなかたでハイレベルに揃えられるお正月準備。
水産加工課係長の伊藤美幸さんに、年末の活きぶりについて情報をもらいました。
さらに上手なお刺身の引き方やなまこ調理のコツについても教えていただきましたよ~。
これは保存版。

ここでは豊前国分寺の屋根瓦を作っています。
その工房跡が復元してあります。工房は縦の長さ30メートル程の吹き抜けの屋根のついた建物が二棟あります。
公園の奥の方、少し高台になったところにあるのが堂がえり釜跡。
ここの釜で豊前国分寺の瓦を焼いたのです。
釜は発掘調査された状態で見学できます。
釜には屋根がつけられ、横に見学用に階段がついたもので、釜の長さが10メートルもあるものです。
下の焚き口に立ち、釜の口からのぞくと、瓦をどうやって焼いたか分かります。
水産加工課係長の伊藤美幸さんに、年末の活きぶりについて情報をもらいました。
さらに上手なお刺身の引き方やなまこ調理のコツについても教えていただきましたよ~。
これは保存版。

この記事はいかがでしたか?
リアクションで支援しよう