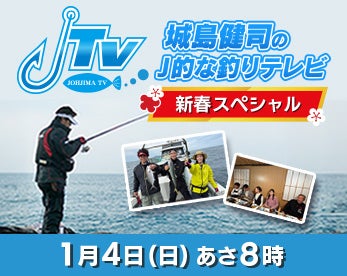テレビの海外ニュースや新聞の国際面の記事で最近、頻繁に使われる言葉がある。それは「常態化」だ。東アジア情勢に詳しい、飯田和郎・元RKB解説委員長がRKBラジオ『田畑竜介 Grooooow Up』に出演し、多用される「常態化」についてコメントした。
好ましくないケースに使われる言葉
まず、国際政治に限らず、この「常態化」という表現を使うケースを挙げてみよう。身近な例を挙げる。「マスクの着用が常態化した」「福岡空港の保安検査場の混雑が常態化している」――。このほか「毎年毎年、巨額の補正予算の編成が常態化している」…。
記事を書く記者がいま、使いやすい、すぐ思いつく表現かもしれない。まさに、記事を書くうえで、「常態化」という単語を使うことが「常態化」している。
多用される「常態化」。国際政治の舞台において、中国に絡んだ事態で使用されることが多い。そして、どれも「よろしくない」ことを指す。日本や台湾に対しての最近の「常態化」をピックアップした。
「沖縄県の尖閣諸島 周辺海域へ、中国の公船(=公の船)の侵入が常態化している」
「沖縄本島と宮古島の間で、中国の艦艇や航空機の通過が常態化している」
「事実上の『休戦ライン』台湾海峡の中間線を無視した、中国の軍用機の訓練や威嚇行為が常態化している」
「常態化」。それを仕掛けた方(=中国)からすると、「既成事実として積み上げる。当たり前にさせる」という狙いがある。
常態化する中国艦艇や航空機の通過、海警局船の滞在
沖縄本島と宮古島の間の海域を、中国の艦艇や航空機が通過するのが常態化している。空母が通過し、その空母では艦載機(=戦闘機)の発着訓練を繰り返す。ここは、中国からすれば、「太平洋への出口」。有事の際にアメリカ海軍の干渉を阻むことができる。
中国の今年の国防費は、日本円で30兆円を超える。伸び率にして前年比で7.2%増だった。30兆円は、日本の防衛予算案の4.5倍。軍拡路線が止まらない。
さらに厄介な「常態化」がある。尖閣諸島沖で、中国の海警局の船の滞在が常態化している。海警局とは、沿岸警備を担当する部門。日本の接続水域(=日本の「領海」の外側水域)での航行は昨年、過去最多の336日に上った。軍拡路線で、能力を高めた船が次々と就航し、長く滞在することが可能となった。
中国海警局は、もともとは日本の海上保安庁と同じ「海の警察」だった。それが今から5年前に組織が改編され、治安維持を担当する人民武装警察部隊(武警)の傘下に置かれた。さらに3年前には、海警局は準軍事組織となった。中国の主張する「領海、領土など主権が侵害された」と判断した場合、外国の船舶への武器使用も認められる。
昨年11月には、76ミリ砲を搭載した海警局の船が初めて日本の領海(=接続水域の陸地側。基線と呼ばれる陸側から起算するポイントから約22キロの水域)に侵入した。海軍とは別組織なのに、武装化が進む。
領海への侵入で言うと、つい最近のこと。中国海警局の船3隻が4月2日まで連続して80時間36分、尖閣諸島沖の領海に侵入した。尖閣諸島は2012年に国有化されたが、それ以降で最長となった。
日本は離島防衛体制を強化、さらに自衛隊と海保が連携
こうした動きに対し、日本は南西地域の離島防衛体制の強化(=南西シフト)に乗り出した。与那国島、宮古島などへの拠点づくりに続き、4月には石垣島に陸上自衛隊の駐屯地が開所した。
それらに加え、安全保障関連3文書が閣議決定された昨年12月16日、海上保安庁の能力強化に関する新たな方針が決まった。あまり注目を集めていないが、実はこれが重要だ。ポイントは「自衛隊と海保の連携」だ。海保は今後、自衛隊との協力関係を重点に置きながら、体制を構築していく。海保の予算の大幅増も打ち出した。
ただ、海上保安庁の法律との整合性を問われる可能性もある。海上保安庁法の第25条はこう定めている。
「この法律のいかなる規定も、海上保安庁、または、その職員が軍隊として組織され、訓練され、または、軍隊の機能を営むことを認めるものと、これを解釈してはならない」
つまり、「海保を軍事組織として扱ってはならない」という意味だ。
台湾と日本に対し「常態化」の企て続ける中国
そんな中、日本と中国の両政府が海洋問題について話し合う「高級事務レベル海洋協議」が4月10日、東京で開かれた。コロナ禍もあり、対面での開催は4年ぶりだ。日本側は、中国海警局の船による尖閣諸島沖の領海侵入を直ちにやめるよう要求。「台湾海峡の平和と安定の重要性」も訴えた。
一方、中国の海警局によると、中国側は、東シナ海、尖閣諸島などでの日本の海保の巡視を挙げ、「中国の領土主権を侵害するな、事態を複雑にするあらゆる言動を停止すべき」と求めた。
今後、継続協議を約束した項目もあった。だが、この間にも、中国海警局の船が尖閣諸島するなど、事態を「常態化」させようという企てが続く。
台湾に対しても同じ。蔡英文総統のアメリカ訪問への対抗措置として、中国は台湾近海で軍事演習を行った。ただ、演習終了を宣言したあとも、中国の艦船が訓練やパトロールを継続している。「常態パトロール」。中国メディアはこう表現している。中国側がすでに「これは常態。当たり前」という認識を植え付け始めている。
アメリカ軍は「今から3年後にも、台湾有事があり得る」と報告している。これら訓練やパトロールは、台湾侵攻のシミュレーションだ。台湾住民に、ジワジワと圧力をかけるやり方。大規模な軍事演習より効果があるかもしれない。
気になるのは、やはり沖縄本島と宮古島の間を抜け、中国の偵察用無人機が東シナ海と太平洋を往復し始めたことだ。実戦を想定した運用との指摘も、防衛関係者から出ている。この無人機の飛行も常態化させるつもりだろうか。
長野県・軽井沢で開かれたG7外相会議では、「中国の力を背景にした一方的な現状変更の試みに反対する」ことで一致した。「一方的な現状変更の試み」が続けば、「常態化」につながる。地域に不安の種をまくふるまいを、常態化させてはならない。そのことが、日本側のさらなる南西シフトを加速させ、お互いが軍事力・防衛力増強を競う。有効な打つ手がないとすれば、非常に危険だと言えるだろう。
◎飯田和郎(いいだ・かずお)
1960年生まれ。毎日新聞社で記者生活をスタートし佐賀、福岡両県での勤務を経て外信部へ。北京に計2回7年間、台北に3年間、特派員として駐在した。RKB毎日放送移籍後は報道局長、解説委員長などを歴任した。
この記事はいかがでしたか?
リアクションで支援しよう