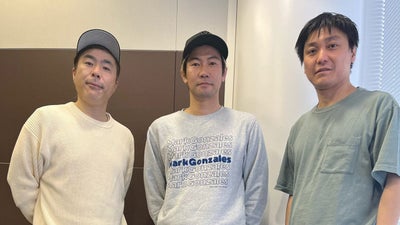目次
徳川家康はあんなに頼りなかったのか?
中学生の時に読んだ、山岡荘八さんの「徳川家康」(講談社、26巻)では、「タヌキ親父」というイメージで描かれています。歴史小説は、日本の歴史的人物に像を与える大きな役割を果たしています。小説もドラマもフィクションですから、『どうする家康』の松本潤さんとあまりにイメージが違うと怒ってもしようがない。いろいろな見方をフィクションやドラマで提供するのは、それはそれで構わないのですが、僕が大河ドラマを「嫌だな」と思うのは、風俗や価値観で「歴史上これはないなあ」ということがあるからです。
歴史を題材にしたフィクションで「絶対変えちゃいけないこと」があります。例えば「徳川家康が何年に死んだか」をずらしてはいけないですね。「九州の生まれだ」ということにしてもいけないです。例外は隆慶一郎さんが書いた歴史小説「影武者徳川家康」(新潮文庫)。家康が関ヶ原の戦いで西軍によって暗殺され、その後影武者が幕府を開いた、という体裁です。史実をずらしていき、歴史小説を成立させる、という特殊なケース。極端な言い方をすればSFに近いんですけど、これは面白かったです。
歴史学の第一歩は「史料批判」
そこで必要なのが「史料批判」です。歴史学を学ぶに当たって最初に必ず習う言葉です。この史料はどういうものなのか、を考える。誰が書いたものか? どんな時に、誰に宛てて? 何の目的で? 5W1Hを確認しながら、そもそもそれが本物なのかどうかを確認していきます。
一番大事なのが「1次史料」。本人やその側近が、そこにいた人しか分からないことを書いているものです。その人たちが言っていたことを書き留めた記録は、伝聞なので「2次史料」です。1次史料がない時は、2次史料をしっかり組み立てて立論していきます。
「安倍晋三回顧録」には歴史的な史料価値がある
「舞台裏のすべてを自ら総括した歴史的資料」と書かれていて、各紙誌で紹介されています。毎日新聞では3月8日、専門編集委員の古賀攻さんがコラム「水説」でこう書いていました。
「すぐベストセラーになったこの本は確かに面白い。特に政界の裏話や海外首脳の人物評は、長くその座にいた者にしか語れない内容がふんだんにある」
歴史の中で検討されていく「史料」
とにかく、書かれていることを鵜呑みにしないことが大事です。冷静に分析していって、ファクトを積み重ねて、実態はどうだったのか、全貌はどうだったのかを確かめていく作業。私は歴史学を学んできて「ジャーナリズムとほとんど一緒だな」と思っています。
本当はどんなことなんだろう? 証拠は何があるの? 証言はどんなものがあるのだろう。それは本当かどうか。その人は「自分にとって都合のいいこと」を言っているのでは? 一緒だなと思います。再び、毎日新聞のコラム「水説」から。
ただし、政権が追い込まれた案件では、根拠が怪しい陰謀論や過剰な自己防衛が顔をのぞかせる。森友学園事件を「私の足を掬(すく)うための財務省の策略の可能性がゼロではない」と言い、検察庁法の改正案は法務・検察当局の要望だったという釈明が代表例だ。(中略)
回顧録が優れているのは、真実に満ちているからではない。最高権力者ならではの強烈な自負心と政策判断のプロセス、特有の猜疑(さいぎ)心がストレートかつ比較的無防備な形で記されているからだ。
「こうあってほしい」という意図は禁物
一番いけないのは、自分が「こうあってほしい」もしくは「こうあってほしくない」という見方を取ってしまうこと。いろいろな見方があるとしても、ファクトは変えられない。繰り返しになりますが「何年に家康が死んだか」は変えられないんです。立場が「リベラル」か「保守」なのかに関わらず「意図を入れて全体像をねじ曲げるのはだめ」。これも原則です。
毎日新聞の古賀さんはこう書いています。
ジャーナリストを名乗る桜井よしこさんは週刊新潮2月23日号のコラムで、官僚が意に反する政治家を倒しに来たと驚いている。そして「国民と日本のために、これほど戦った政治家がいた」ことに「深い感動を覚えた」と。
感動するのは自由だが、読み方に飛躍がある。ジャーナリストにとって仕えるべき主(あるじ)は事実だろう。裏付けのない策略説を基に別の主を作り出すのは、本来この仕事とは無縁の作業である。
中曽根さんの自己認識「歴史の法廷で裁かれる立場」
「今は言えないけれど、いずれ後世の人は評価してくれるんじゃないか」と思って隠しているということは、政治の中では起こることです。例えば、日米沖縄密約問題ですね。歴史法廷において「この人がやったことはどうだったんだろう?」ときちんと分析をされていくわけです。
そこには、忖度なんてありません。だから歴史は怖い。それを中曽根さんはよく分かっていました。自分は歴史法廷に立つことになる。裁かれる私は、生前のうちに被告人としての陳述をしておきたい。タイトルに込めたのは、そういう趣旨だと思います。自分は間違ったことはしていない。だからこそ「被告席に立つのだ」と言い切れるわけです。
安倍さんも、言うべきことを遺しておきたい、と思ったのかもしれません。一部には過剰な防衛の心や、猜疑(さいぎ)心が比較的無防備な形で記されています。つまり、かなりの一級資料だと言っていいのでしょう。ただし、「書かれていないことは何なのか?」という分析もとても重要です。
保守とは「歴史に対して謙虚であること」
「保守」とは、中曽根さんのように、歴史認識に対する謙虚さを持つ人だ、と私は思います。もし、一貫して認めなければ、いつかはやり過ごせると政治家が思っているとしたら、歴史の重みに価値を置く「保守」とは言えないでしょう。いずれ歴史の法廷で、厳しく裁かれるでしょう。
もし仮に「今言えないこと」があり、国会で一切認めなかったとしても、いずれそれがバレたところで私は間違っているとは思わないので、裁いてほしい。こういう姿勢が「歴史の価値を大事にする」保守としてはわかりやすい。逆に言えば、歴史に価値を置かない人は、いずれ裁かれるなんて考えていないということです。今隠せればいいと思う人を「保守政治家」と言えるのか? という問題が今、目の前で繰り広げられる気がします。
安倍さんの回顧録、私もまだ買っただけなので、これから読んでみようと思っています。書かれていないことは何なのか、も考えながら。
◎神戸金史(かんべ・かねぶみ)
1967年、群馬県生まれ。毎日新聞に入社直後、雲仙噴火災害に遭遇。福岡、東京の社会部で勤務した後、2005年にRKBに転職。東京報道部時代に「やまゆり園」障害者殺傷事件を取材してラジオドキュメンタリー『SCRATCH 差別と平成』やテレビ『イントレランスの時代』を制作した。中曽根康弘氏は高校の先輩で、3年生の時に現職総理だった中曽根氏と対談したことがある。
参考までに……中曽根康弘さんの「自省録」より
第1章「政治家が書き遺すことの意味」から引用(16~18ページ)
政治家にとって人生とは結果でしかありません。
思想家はその思索の跡を膨大な著作物に遺し、作家なら作品という形で後世に評価を問うことが可能です。さらに、時代とともに社会を見据えるジャーナリストなら、優れた時代評論として巷間につたえることもできます。
しかし、政治家は達成した現実だけが著作であり、作品なのです。しかも、その評価は、読者の数によって決められるものでもなければ、凝らされた修辞の妙によって賞賛されるものでもありません。政治家の人生は、その成し得た結果を歴史という法廷において裁かれることでのみ、評価されるのです。(中略)
私の政治生活を一言でいうなら、「戦後政治の総決算で、敗戦の結果失われた良きものを取り返し、日本の本来の扉を開くこと」でした。つまり芭蕉の言う「不易と流行」です。そのために、日本と世界の未来を押し開く政策を展開してきました。そのことを書いたこれまでの論考は、歴史という法廷に立たされる当事者の自己弁護と映るかもしれません。
しかし、歴史法廷は、私の自己弁護などそのまま受け入れるとは思えません。歴史は、私の意図などをはるかに超えた巨大なうねりであり、強大な力です。
今の私には、数年前よりいっそう鋭く歴史が見えるのです。不思議なものですが、人間は年齢を経るごとに、巨大で強力な歴史の流れを個人の力では到底動かしがたいものであることを知る。積み重ねられた知識と論理が、いやがうえにも歴史の不可抗性を教えるのです。
しかし歴史の法廷がどう裁こうが、政治家は目の前の現実に対処していかなければなりません。その責務を逃げずに果たしてこそ、政治家と言えるのです。ここには、熾烈な重圧があります。翌日の新聞に踊る大きな批判記事の活字など、たいした問題ではなく、この国の将来は自分の決断ひとつにかかっていると感じたときの恐ろしいほどの重圧感です。その重圧感に立ち向かわせるのが、若き日の直感と、成熟により獲得した知恵なのです。
この記事はいかがでしたか?
リアクションで支援しよう