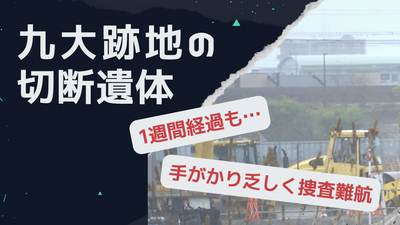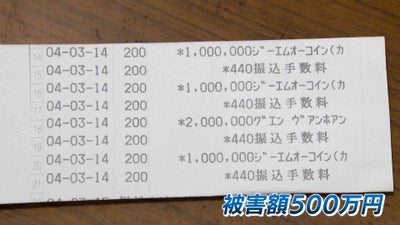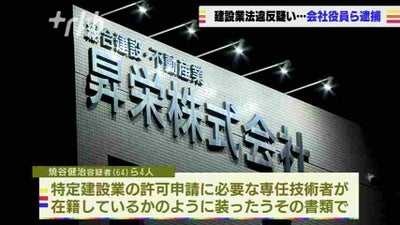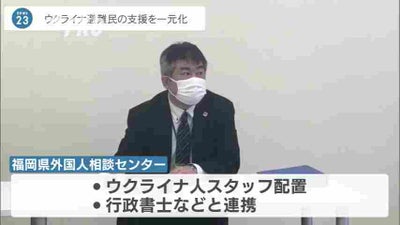<リード>
6月はRKB70周年を記念した「カラフルマンス」として、SDGs=持続可能な開発目標への様々な取り組みを紹介しています。
今回は9番「産業と技術革新の基盤をつくろう」です。
水害や地震などの災害が多発する日本では、生活に欠かせない道路や河川の治水施設などのインフラ設備が、被害に遭うことも少なくありません。
被害を最小限に抑え少しでも早く復旧させるため、国は最新技術を駆使した対応を進めています。
<VTR>
記者リポート「こちらのモニターでは、360度の映像を見ることができます。さらに、この画像を使うことで、川幅の測量も簡単にできてしまいます」
福岡市博多区にある国土交通省・九州地方整備局。
九州の道路や河川の治水施設など、多くのインフラ設備を管理していています。
ここ数年、毎年のように発生している大きな水害や地震などから、インフラ設備を守り被害を受けた場合は、いち早く対応することが求められています。
その鍵を握るのは、情報の早さと正確性です。
インタビュー
活用しているのは360度撮影できるカメラで撮られた画像です。
インタビュー
この機能を最大限にいかすため、九州地方整備局が開発したのは「災害情報共有クラウドシステム」です。
「災害情報共有クラウドシステム」は、災害現場で撮影した360度の画像を、インターネット上のデータの置き場所=クラウドに保存。
保存された写真などのデータは、九州地方整備局や九州各県に設置された災害対策本部などで、リアルタイムで共有することができます。
この新たなシステムを使うことにより、災害発生前や発生直後に素早く対応することが可能となりました。
インタビュー
九州地方整備局は、新たなシステムの導入も進めています。
インタビュー
モニターに立体的に映されているのは、レーザーで計測する特殊な機械を使って、地形のデータを収集し無数の小さな点で表示した「点群データ」です。
被災した河川を上下左右、様々な角度から見ることができます。
インタビュー
この「点群データ」を使うと、モニター上で測量もできるため、被災後の復旧対応が早くなることが期待されています。
インタビュー
「点群データ」は、早ければ今月中に導入される見通しです。
道路や河川の治水施設など、インフラ設備の災害による被害を最小限に抑えるとともに、少しでも早い復旧を実現させるため、国は最新技術を駆使した対応を進めています。
この記事はいかがでしたか?
リアクションで支援しよう
radiko 防災ムービー「いつでも、どこでも、安心を手のひらに。」