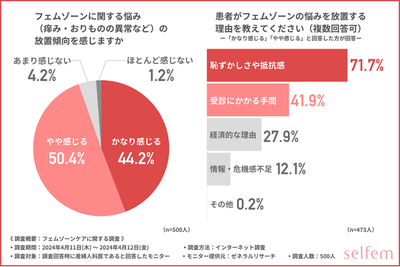国連が提唱する持続可能な開発目標=「SDGs」を考えるシリーズ。17の目標の中から今回取り上げるのは、こちら「ジェンダー平等の実現」です。「6.16%」という数字。これは、昨年度の男性の育児休業の取得率です。日本人男性の育児に関わる時間は、先進国の中でも特に少ないと言われています。この状況をどう変えていけばいいのか、実際に育休を取得した男性たちを取材しました。
福岡県職員の小河利紀さん。長女の桜ちゃんが去年4月に生まれ、1年間、育児休業を取得しました。民間企業で働く妻の美鈴さんも育休を取っていて、この日は3人で近くのベビー用品店に買い物にやって来ました。
小河さんは、妻が妊娠5か月の時に職場の上司に育休を取得したいと相談しました。
春に部署の異動があったものの、事前に伝えていたこともあり、子供が生まれてからスムーズに、育休を取得できたといいます。休みの間に共済組合から支給される育児休業手当金は、半年間は賃金の67%、1歳になるまでは50%となります。ただ、夫婦にとっては給料が減ったとしても、得られるものは多いようです。
男性の育児休業の取得率は、昨年度は6・16%、政府は2020年中に、13%に上げることを目標としていますが、達成は難しい状況です。また育休を取得した期間も、女性が「10か月~1年」が最も多いのに対して、男性は「5日未満」がおよそ4割を占めています。福岡市中央区のウェブ制作会社で働く新津圭祐さんは去年、2人目の子供が生まれた時に1か月間、育休を取得しました。
2000年創業で、若い社員が多い職場ですが、これまで男性で育休を申し出た人はいなかったため、会社側も当初は対応にとまどったそうです。
男性社員の育休取得に前向きに取り組むことは、会社側にとっても、求人面で大きなアピールポイントとなります。
育休を取ることで、子育てに対する意識が変わるという意見もあります。福岡県職員の斉藤健治さんは6年前、長女が生まれた時に5か月間育休を取得し、ニュースでその模様を放送しました。その後長男も生まれ、家では「イクメンパパ」として、料理など家事も積極的にこなしています。
育休を取る理由は、人それぞれ違います。まずは職場の理解を深め、休みを取りやすい環境を整えていくことが、第一歩となります。
福岡県職員の小河利紀さん。長女の桜ちゃんが去年4月に生まれ、1年間、育児休業を取得しました。民間企業で働く妻の美鈴さんも育休を取っていて、この日は3人で近くのベビー用品店に買い物にやって来ました。
小河さんは、妻が妊娠5か月の時に職場の上司に育休を取得したいと相談しました。
春に部署の異動があったものの、事前に伝えていたこともあり、子供が生まれてからスムーズに、育休を取得できたといいます。休みの間に共済組合から支給される育児休業手当金は、半年間は賃金の67%、1歳になるまでは50%となります。ただ、夫婦にとっては給料が減ったとしても、得られるものは多いようです。
男性の育児休業の取得率は、昨年度は6・16%、政府は2020年中に、13%に上げることを目標としていますが、達成は難しい状況です。また育休を取得した期間も、女性が「10か月~1年」が最も多いのに対して、男性は「5日未満」がおよそ4割を占めています。福岡市中央区のウェブ制作会社で働く新津圭祐さんは去年、2人目の子供が生まれた時に1か月間、育休を取得しました。
2000年創業で、若い社員が多い職場ですが、これまで男性で育休を申し出た人はいなかったため、会社側も当初は対応にとまどったそうです。
男性社員の育休取得に前向きに取り組むことは、会社側にとっても、求人面で大きなアピールポイントとなります。
育休を取ることで、子育てに対する意識が変わるという意見もあります。福岡県職員の斉藤健治さんは6年前、長女が生まれた時に5か月間育休を取得し、ニュースでその模様を放送しました。その後長男も生まれ、家では「イクメンパパ」として、料理など家事も積極的にこなしています。
育休を取る理由は、人それぞれ違います。まずは職場の理解を深め、休みを取りやすい環境を整えていくことが、第一歩となります。
この記事はいかがでしたか?
リアクションで支援しよう