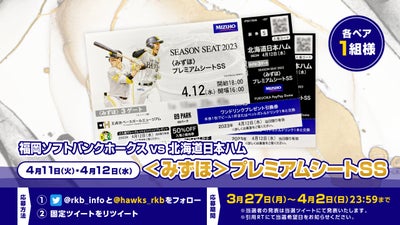しかし、FAISの試作品は1機が数千万円という高価格であった。石川鉄工所は町工場ならではの技術と感覚を駆使。試作品の精密検査を行うための様々な先進機能や自立稼動を目的とした電子機器を徹底的に廃し、実際の現場で求められる機能に絞り、悪路走行に絶えうる数百万円代のロボットを製作するに至った。現在はJR九州の線路下にある配管、中東のパイプラインなど様々な場面で検査に採用されている。
石川鉄工所では「もぐりんこ」シリーズだけでなく、様々なニーズに応え、医療用の検査装置や測定装置なども製作。既製品ではできない痒いところに手が届く機能と価格を実現。さらに「もぐりんこ」を応用し特殊な環境で検査ができる高圧電線用の検査ロボットを製作した。
ブランド名:もぐりんこ(管渠検査ロボット)
取材対象者:石川 清光(いしかわ きよみつ)
所在地:福岡県北九州市八幡西区則松472
電話:093-691-4466
HP:http://iiw-future.com/
協力
・北九州市上下水道局 平野哲 係長・山口秀和 主査
住所:〒803-8510福岡県北九州市小倉北区大手町1-1
電話:093-695-3046
・北九州学術推進機構 国家戦略特区ライン 善甫英治 グループ長
住所:〒808-0138福岡県北九州市若松区ひびきの北1番103
電話:093-582-2480
・九州工業大学 大学院生命体工学研究科 石井和男 教授
住所:〒808-0196福岡県北九州市若松区ひびきの2-4
電話:093-695-6102
取材後記
この「もぐりんこ」取材の話をいただいたとき、やはり一番知りたかったのは、なぜこれを作ることになったのか?ということです。
従来品はもっと高価で操作が難しい。そのため専門業者しか操縦できない。もちろんもぐりんこはそれを淘汰するほど万能というわけではなく、精密検査の前に水道局の職員が自ら操縦することでスクリーニング(簡易的な選別・審査)を行うという発想で作られているのです。
石川鉄工所はモノづくりのまち北九州にありますが、ディレクターである私も北九州市で育ち、エンジニアの息子でもあります。石川鉄工所でもぐりんこを開発している石川社長のモノづくりに対する考え方を聞いていると、かつて父の話していたモノづくりの考え方と共通するものが多いことに気づきました。
たとえば頑丈な既製品を使って値段を安くすること、シンプルに作ること、使いやすいことなど。現代ではロボットといえばどうしても人工知能を搭載したり、複雑な機構を搭載し、実験ショーみたいになってしまいがちですが、使う側のことを考えるとそんなものは必要ないし、壊れやすく、高価になるわけです。
何より石川社長の言っていたことに「機能美」というものがあります。いろんな装備を次々足していくと、どんどんゴツゴツした戦車のようになっていく。しかし最低限の部品だけでシンプルさを追求して作っていくと、美しいデザインになっていく。使う側にとっても雑情報がなく、抵抗がなく使えるものになっていく。そういった「機能美」を追求していくという考え方はエンジニアである私の父の考え方にそっくりだと思いました。
今の40才以下の世代はファミコン世代であり、さらに若い世代はもっと進化したゲームやパソコン、さらにスマートフォンなどといった高性能の電子端末に囲まれて暮らし、それがあたりまえとなっています。私も含めて若い世代がもしも「もぐりんこ」のようなロボットを作ろうとしたとき、こういった電子機器を使用し、自動化することを当たり前としてしまうのではないでしょうか?そうだとしたらもぐりんこのようなシンプルロボットをつくることができるでしょうか? 石川社長も私の父も世代的にも近く、コンピューターやマイコンどころかICや電子装置もない時代から機械の設計・開発をしていた世代であり、最低限のモーターや機構を使ってモノづくりをしてきたため、電子装置を使わず作る能力を持った世代でもあります。だから共通して「シンプル」というテーマを追求するのだと思います。したがって、もぐりんこのようなロボットを作ろうという発想はこの世代からしか生まれないのではないかと思うのです。
一方で石川鉄工所という会社のスタンスももぐりんこを生み出した土台になっているとも感じました。もぐりんこを筆頭とした「痒いところに手が届く」石川製品は大手では作ることができないと思います。価格が安く、生産量も少ない上、頻繁なモデルチェンジや顧客ごとの仕様変更が求められる。これは大企業のビジネスモデルとしては成立しないと想像できます。たくさんの部署で長時間審議され、マーケティング情報を重視するあまりビジネスライクな付加価値を追求しがちな大企業では難しいことが想像できるのです。
石川鉄工所にはある程度の従業員数がいて、モノづくりの技術もある。経営だけでない技術に長けたリーダーがいることは「痒いところに手が届く」石川製品が生み出される母体ともなっているわけです。
こういった石川社長の世代的エンジニア気質、石川鉄工所という環境。これらがもぐりんこ開発の主軸をスクリーニングという考え方に絞ること、シンプルロボットの誕生につながったと思うのです。
この記事はいかがでしたか?
リアクションで支援しよう