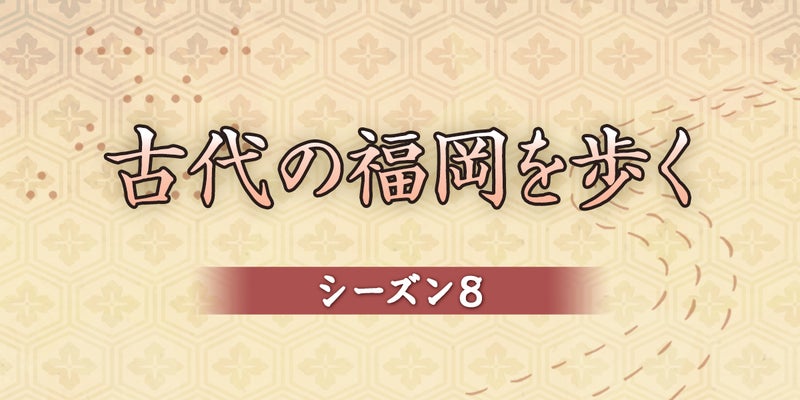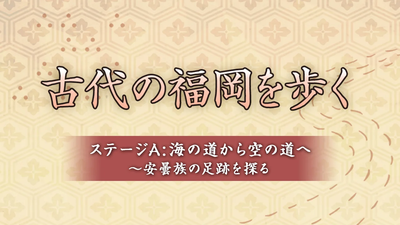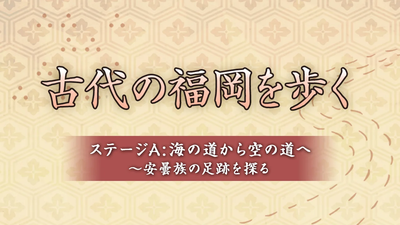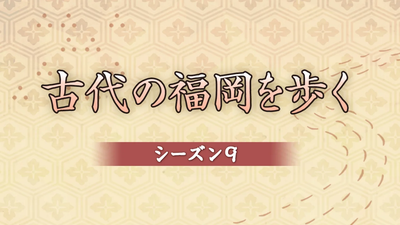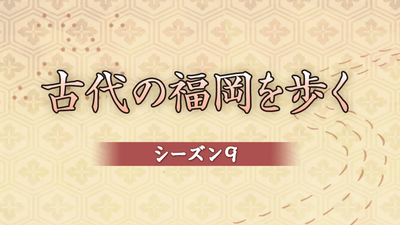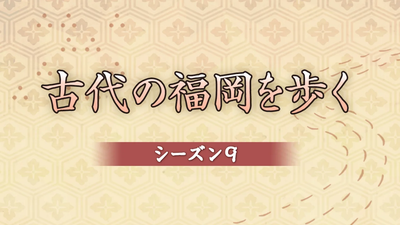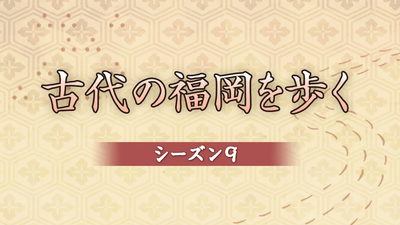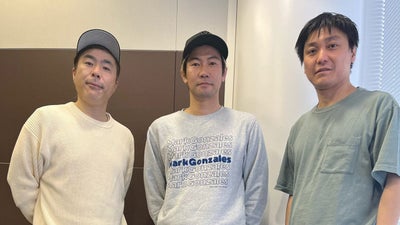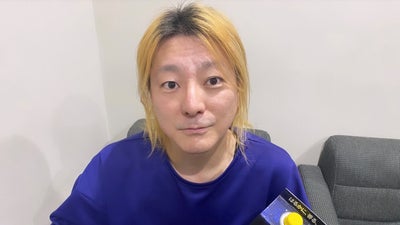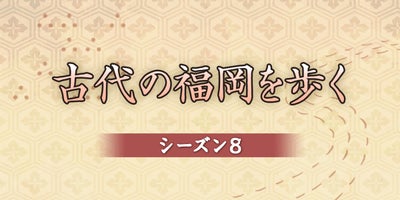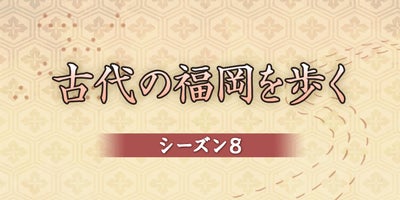8回目は唐津と糸島の境目にやってきました。海岸をみますと、全く奇妙な岩が一つ、そそり立っています。
大きさは4~5メートル、幅2メートル程の立方体の岩です。下の土台の部分は四角や三角の岩を組み合わせて立法体の岩を人が作ったみたいな感じでできています。
そして、頭の部分には丸い2メートルくらいの岩が載っているのです。
これが、鼓石といわれるもので、何でも鼓の形をしているからだということでした。
かつてはこの岩を境に海に向かって右側が筑前、左側が肥前といったとか。
ここには、測量のために伊能忠敬も訪れたと標識には書いてありました。
それにしても、奇妙な岩があったものです。
そして、岩から海岸に上がり、国道の向こう側にあったのが七郎神社。
小さな洞窟の中に祠があり、木刀がたくさん奉納してありました。
この神社にも木刀にまつわる面白い伝承がありました。 「リツ子・その愛/その死」、「火宅の人」などを書いた福岡県出身の小説家・檀一雄ゆかりの寺が、みやま市の平田・善光寺。妻・リツ子を亡くした後、昭和21年6月から11月まで、息子の和雄とともに善光寺の庫裏の二階で暮らしています。
「リツ子・その愛/その死」、「火宅の人」などを書いた福岡県出身の小説家・檀一雄ゆかりの寺が、みやま市の平田・善光寺。妻・リツ子を亡くした後、昭和21年6月から11月まで、息子の和雄とともに善光寺の庫裏の二階で暮らしています。
実はお寺と檀一雄を引き合わせたのが、郷土史家で『誰にも書けなかった邪馬台国』の著者・村山健治さん。
現在92歳になった当時のご住職の娘さん・原口ひろえさんにいろんなエピソードを聞かせてもらいました。
檀一雄が見た、歌に詠んだ風景が今でも善光寺の境内から眺められます。


大きさは4~5メートル、幅2メートル程の立方体の岩です。下の土台の部分は四角や三角の岩を組み合わせて立法体の岩を人が作ったみたいな感じでできています。
そして、頭の部分には丸い2メートルくらいの岩が載っているのです。
これが、鼓石といわれるもので、何でも鼓の形をしているからだということでした。
かつてはこの岩を境に海に向かって右側が筑前、左側が肥前といったとか。
ここには、測量のために伊能忠敬も訪れたと標識には書いてありました。
それにしても、奇妙な岩があったものです。
そして、岩から海岸に上がり、国道の向こう側にあったのが七郎神社。
小さな洞窟の中に祠があり、木刀がたくさん奉納してありました。
この神社にも木刀にまつわる面白い伝承がありました。
実はお寺と檀一雄を引き合わせたのが、郷土史家で『誰にも書けなかった邪馬台国』の著者・村山健治さん。
現在92歳になった当時のご住職の娘さん・原口ひろえさんにいろんなエピソードを聞かせてもらいました。
檀一雄が見た、歌に詠んだ風景が今でも善光寺の境内から眺められます。


この記事はいかがでしたか?
リアクションで支援しよう