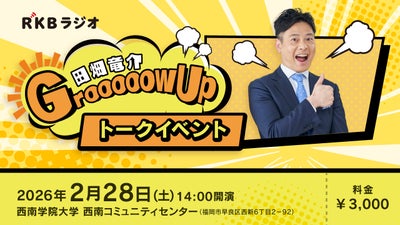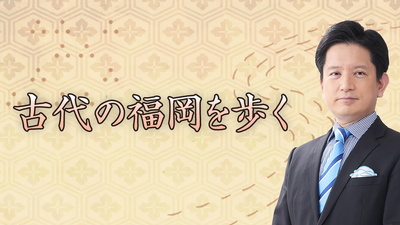3月28日、ミャンマー中部をマグニチュード7.7の大地震が襲い、甚大な被害をもたらしました。この地震の被害はミャンマー国内にとどまらず、タイの首都バンコクでも被害が発生しています。国際情勢に詳しい、飯田和郎・元RKB解説委員長が3月31日のRKBラジオ『田畑竜介 Grooooow Up』に出演し、今回の大地震をめぐる各国によるミャンマー支援と国際政治、そして、被災地と日本の歴史的関係について解説しました。
ミャンマー大地震:被災地の現状と国際社会の動き
最新の被害状況は、情報の錯綜もあり、まだ正確な数字を把握することが難しい状況です。ミャンマー国内では多数の死者が出ているほか、家屋やインフラが広範囲に破壊され、救助活動は困難を極めています。
この地震の被害は、タイの首都バンコクでも建設中の高層ビルが倒壊するなどの被害が発生し、救出作業が続けられています。また、ミャンマーの北に位置する中国でも、地震による影響が出ていることが報告されています。
軍政下のミャンマー:国際社会の支援と政治的思惑
ミャンマーでは、2021年2月に発生した軍事クーデター以降、軍部が全権を掌握し、現在も軍政が続いています。国内では民主派勢力による抵抗運動が続いており、各地で軍との衝突が発生するなど、政情は不安定な状態です。
そのような状況下で発生した今回の地震に対し、ミャンマー軍政は地震発生当日、国際社会に向けて人道支援を求めました。これに対し、中国、ロシア、インドなどが迅速な支援活動を開始したことが注目されます。
特に中国は、地震発生からわずか18時間後に救助隊を現地に派遣するという異例の早さを見せました。中国の救助隊は、レスキュー隊や医療班で構成され、医療品、テント、毛布などの支援物資のほか、捜索用のドローンや生き埋めになった人を探す感知センサーなども携行しました。中国国営メディアは、この救助隊が「ミャンマーに到着した最初の国際救助隊だ」と報じています。
ロシアも地震発生当日に、輸送機2機を使って120人規模の救助隊や災害救助犬をミャンマーに派遣しました。ロシアのメディアは、この迅速な対応が「プーチン大統領自身の指示によるものだ」と伝えています。
これらの国々の動きからは、ミャンマー軍政との関係の緊密さ、そしてそれぞれの国の政治的思惑が垣間見えます。
中国:中国にとって、ミャンマーは中国から国外に延びる巨大経済圏構想「一帯一路」の重要な拠点であり、経済的な結びつきが強い国です。また、半導体生産に欠かせないレアアースの採掘量のシェアで、ミャンマーは世界第3位であり、ミャンマー産レアアースの大半を中国企業が買い取っているという事実も、中国の関心を高める要因となっています。
ロシア:ロシアとミャンマーの関係は、主に武器の取引に代表されます。国連の報告によると、ミャンマーではロシア製の戦闘機が学校や医療施設、民家への攻撃に使用されているという情報もあります。また、ミャンマー軍政のトップであるミン・アウン・フライン最高司令官がモスクワを訪問し、プーチン大統領と会談するなど、両国の関係は緊密です。ロシアもミャンマーも欧米諸国から制裁を科されているという共通の立場も、両国間の連携を強める要因となっていると考えられます。
インド:インドは、国連の場などにおいて、ミャンマーに関する決議で拒否権や棄権を繰り返すなど、ミャンマー軍政を擁護する立場を取っています。また、ミャンマー国軍記念日の軍事パレードに代表が出席するなど、ミャンマー軍政との関係は良好です。
これらの国々は、ミャンマーへの迅速な支援を通じて、国際社会における自国の影響力を示そうとしていると考えられます。また、欧米諸国と対立する独裁国家などに対して、「中国やロシアと友好関係を築けば、このような支援を受けられる」というメッセージを送る狙いもあるかもしれません。
国連の場でも、ミャンマー問題に対する国際社会の意見は分かれています。ミャンマーに関する決議において、常任理事国である中国やロシアに加え、インドも拒否権を行使したり、棄権したりすることが多く、欧米諸国との間で立場が大きく異なっています。
被災地と日本の歴史的関係
地震の震源地であるミャンマー中部のサガイン地域は、ミャンマー第二の都市であるマンダレーのすぐ近くに位置しています。この地域は、第二次世界大戦中、旧日本軍とイギリス軍との間で激しい戦闘が繰り広げられた場所であり、日本にとっても深い歴史的なつながりを持つ場所です。
1942年、旧日本軍はビルマ(現在のミャンマー)のほぼ全域を占領しました。その目的は、アメリカやイギリスがビルマを経由して中国を支援する補給ルート(蒋援ルート)を遮断することと、イギリス領だったインドへの打撃を加えることでした。
1944年には、ビルマからインド北部の都市インパールへ侵攻する「インパール作戦」が実行されました。この作戦は、「最も過酷で、最も無謀な作戦」と言われるほど、多くの犠牲者を出した作戦として知られています。マンダレーには日本軍の拠点が置かれ、サガイン周辺でもイギリス軍との激戦が繰り広げられました。ビルマに派遣された日本の兵士約20万人のうち、約9割にあたる18万人が戦闘や飢え、病気などで命を落としたと言われています。
サガインやマンダレーには、戦死した日本兵や病死した日本兵のために、戦後、遺族や戦友によって数多くの慰霊塔やパゴダ(仏教寺院)が建立されました。これらの慰霊施設は、仏教への信仰が篤い現地のビルマ人(現在のミャンマーの人々)の理解と協力によって実現したものです。
今回の地震では、マンダレーの仏教寺院やビルなどの多くの建物が倒壊したという情報が入っています。旧日本兵の霊を慰める施設も、被害を受けている可能性が高いと考えられます。
このように考えると、今回の地震は、単に「遠いミャンマーで起きた地震」として捉えるのではなく、国際政治の複雑な思惑が絡み合う中で、日本とも深い歴史的なつながりを持つ地域で発生した災害として、より深く理解する必要があると言えるでしょう。
この記事はいかがでしたか?
リアクションで支援しよう
この記事を書いたひと

飯田和郎
1960年生まれ。毎日新聞社で記者生活をスタートし佐賀、福岡両県での勤務を経て外信部へ。北京に計2回7年間、台北に3年間、特派員として駐在した。RKB毎日放送移籍後は報道局長、解説委員長などを歴任した。2025年4月から福岡女子大学副理事長を務める。