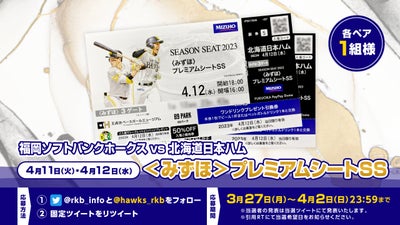□ 駒ヶ根シルクミュージアム →
https://komagane-silk.com/
□ 長野伊那谷観光局 →
https://www.inadanikankou.jp/
□ 駒ヶ根観光協会 →
http://www.kankou-komagane.com/index.php
□ 長野県公式観光サイト →
https://www.go-nagano.net/
□ FDA フジドリームエアラインズ →
http://www.fujidream.co.jp/
![]()
駒ヶ根市があるのは、長野県の真ん中より少し南のあたり…諏訪湖から流れ出る天竜川に沿ったエリアが伊那谷。
西に中央アルプス、東に南アルプスの3000m級の山々が連なるところです。
伊那谷の養蚕・製糸の歴史から、最新の蚕の研究まで、幅広い視点でシルクをとらえた博物館が「駒ヶ根シルクミュージアム」です。
館長の中垣雅雄さんに案内していただきました。
入口がまずすごい!結城紬や大島紬、伊那紬などなど、絹織物の反物がずらりと並んだトンネル状態なのです。
「各地の紬を見比べられる仕組みはなかなかないと思いますよ」と、中垣館長。
おっしゃるとおりです~。見ててわくわくする空間です。
そして、ミュージアムには驚きの展示物が!

館長曰く「蚕の日本一大きな精密模型」。実際の大きさの30倍だそう。
本当の蚕は大きくなっても長さ7~8cm。
30倍だから2.4m。「最近のお子さんは蚕を見たことない人もいるし、『こういうところに模様がある』とか『こんな風に足がついてる』とか、よくわかります。」と、館長。
いやあ、昭和のお子さんだった私も、初めて知ったことだらけです。
脇腹のポチポチ模様は、人間でいうと鼻の役割だそう。

巨大模型の隣にある、ドーナツ状で蚕の体内の仕組みがわかるように作られた模型もなかなかシュールです。
目のように見える正面の黒い点は実はただの模様。
ほかの虫に「お。こいつデカいな…」と、よけさせるための作りだそうです。
口にように見える先頭の茶色のところはいわば顔。
サイドにある小さい6つずつの粒々が目の役割で、明るさだけど見てるそうです。


昭和初めごろの、伊那谷の養蚕農家の復元もあるのですが、関東地域など他の地域が二階の部屋を養蚕に使うのと異なり、平屋の母屋で飼っていたのが特徴的だそうです。


このシルクミュージアムは、養蚕農家が共同出資して作った製糸会社「龍水社」の記録を残していきたいという思いも反映されています。
繭を出荷するだけでは、仲介業者に安く買いたたかれたり値切られたりという状況になりやすかったので、「自分たちで製糸会社を作り、繭を糸にして出荷すれば、高値で取引できるようになる」と、組合を作り出資金を出して製糸会社にしたのだそう。
成功して、平成9年までここで糸取りをしていたそうです。


館長の話を聞けば聞くほどおもしろい、そしてまだまだ見聞きしてないシルク情報ももりだくさんの「駒ヶ根シルクミュージアム」。
またおじゃまして勉強したい!楽しい博物館ですよ~。
この記事はいかがでしたか?
リアクションで支援しよう