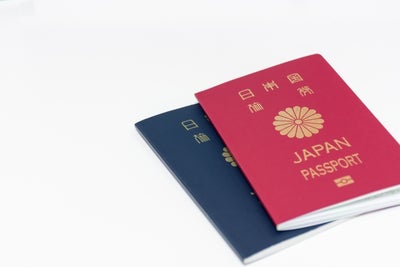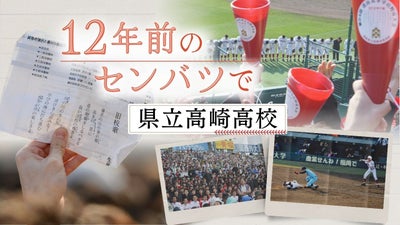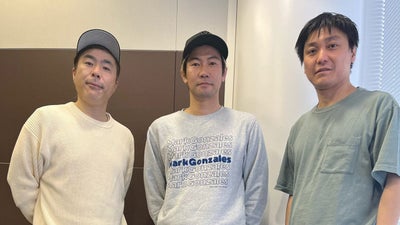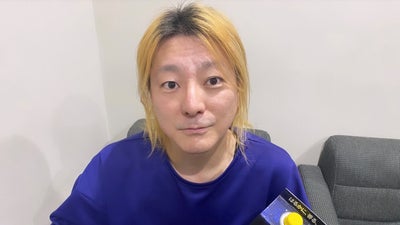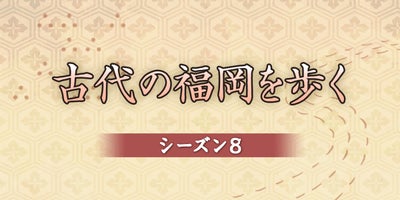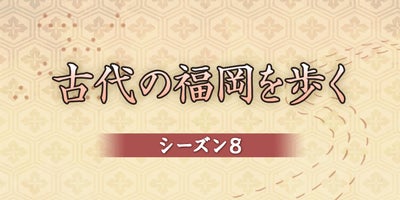目次
反戦ソングとして有名なのは、ジョン・レノンの「イマジン」やボブ・ディランの「風に吹かれて」。そんな中、RKBラジオ『田畑竜介 Grooooow Up』に出演した音楽プロデューサー・松尾潔さんは「そこまで有名ではないかもしれないが、今ちょっと耳を傾けてみたいという曲」を紹介した。
John Mayer「Waiting On The World To Change」(2006)
今のアメリカのミュージックシーンを代表するアーティストの1人です。心地よく聞けるのがJohn Mayerの曲作りのうまさでもあるんですけど、彼は歌声もモテボイスで、ギターがなんといっても天才的という、スーパーなアーティストですが、歌詞にも耳を傾けたいと思います。
サビの部分で「今既にあるシステムを破壊するのは難しいんだけれども。特に自分たちが離れ離れの状態にいて、何かに向き合っているときっていうのは、システムを変えるのは難しい。だからこそ今、世界が変わるのを待っているんだ」と歌っています。要するに今ある世の中とか、今のこの世界政治のシステムに対して問題意識を促していくということなんですね。
また2番の頭では、より具体的な描写が出てきて「もし自分たちに権力というものがあったら、近所の人たちが戦争に行っているのも戻ってこさせることができるのにな」って。アメリカでは、家族が戦争に行ったら、玄関に黄色いリボンをかけて「今うちの家族は国民のために戦っています」っていうのを示す習慣があるんですが、そのリボンを外させることができるのになって。
これこそポップミュージックの魅力だと思うんだけど、日常レベルの出来事の目線で、より大きな国とかシステムに対しての異議申し立てをしてるっていう。また「待つ」って言葉って弱き者の選択肢のように思われるけれども、待つということも積み重ねると、力になるということを教えてくれる曲でもあります。
サビの部分で「今既にあるシステムを破壊するのは難しいんだけれども。特に自分たちが離れ離れの状態にいて、何かに向き合っているときっていうのは、システムを変えるのは難しい。だからこそ今、世界が変わるのを待っているんだ」と歌っています。要するに今ある世の中とか、今のこの世界政治のシステムに対して問題意識を促していくということなんですね。
また2番の頭では、より具体的な描写が出てきて「もし自分たちに権力というものがあったら、近所の人たちが戦争に行っているのも戻ってこさせることができるのにな」って。アメリカでは、家族が戦争に行ったら、玄関に黄色いリボンをかけて「今うちの家族は国民のために戦っています」っていうのを示す習慣があるんですが、そのリボンを外させることができるのになって。
これこそポップミュージックの魅力だと思うんだけど、日常レベルの出来事の目線で、より大きな国とかシステムに対しての異議申し立てをしてるっていう。また「待つ」って言葉って弱き者の選択肢のように思われるけれども、待つということも積み重ねると、力になるということを教えてくれる曲でもあります。
The Impressions「People Get Ready」
Curtis Mayfieldという、ソウルミュージックの世界で大変有名な、シカゴ出身の黒人アーティストがいるんですが、その人が昔、The Impressionsってグループをやっていたときの「People Get Ready」という曲。戦争というよりも、アメリカにおける人種差別をなくそうという公民権運動のテーマソングになったような曲で、ロッド・スチュアートがジェフ・ベックと一緒にやった80年代のカバーバージョンをご記憶の方も多いかもしれませんね。
こういう社会的なメッセージソングっていうのが、それとわかるように、声高に叫ばなくても、ずっと連綿と連なる歴史の中で、今John Mayerも歌っている。こういう歌ってのはアメリカのポップミュージックの世界にはあるんですよね。
こういう社会的なメッセージソングっていうのが、それとわかるように、声高に叫ばなくても、ずっと連綿と連なる歴史の中で、今John Mayerも歌っている。こういう歌ってのはアメリカのポップミュージックの世界にはあるんですよね。
Marvin Gaye 「What's Going On」(1971)
続いてもう1曲。Marvin Gaye の「What's Going On」。1971年の曲なんで、僕もこれ、小学生の終わりか中学生の頭ぐらいですかね、。自然に耳に入ってきてはいたんですけど、このメロウなサウンドが反戦歌って全然知らなかったですね。今も知らない方もいらっしゃるかも知れない。なぜかっていうと知り合いの結婚式で流れてるの聞いたことあるから。
これってMarvin Gayeの弟さんで、フランキーって人がいるんですけど、フランキーがベトナム戦争に行って、ベトナムから戻ってきたのをお兄さんのMarvin Gayeが聞いて、「今、ベトナムの戦線ってそんなことになってるんだ」っていうところから始まった曲なんで、もう紛れもなく反戦歌なんですよね。
これMarvin Gayeが所属していたモータウンレコードの反対を押し切って「この形じゃないと出したくない」って言って、ベリー・ゴーディっていう、ちょっとコワモテの社長が止めるのを振り切って出した。そしたらその会社が始まって以来のヒットアルバムになって、モータウンレコードはまたもっと有名になったっていうような、そういう逸話も残っています。
これってMarvin Gayeの弟さんで、フランキーって人がいるんですけど、フランキーがベトナム戦争に行って、ベトナムから戻ってきたのをお兄さんのMarvin Gayeが聞いて、「今、ベトナムの戦線ってそんなことになってるんだ」っていうところから始まった曲なんで、もう紛れもなく反戦歌なんですよね。
これMarvin Gayeが所属していたモータウンレコードの反対を押し切って「この形じゃないと出したくない」って言って、ベリー・ゴーディっていう、ちょっとコワモテの社長が止めるのを振り切って出した。そしたらその会社が始まって以来のヒットアルバムになって、モータウンレコードはまたもっと有名になったっていうような、そういう逸話も残っています。
Stevie_Wonder「Front Line」(1982)
Marvin Gayeと同じモータウンレコードに所属していた、もう1人の天才Stevie_Wonderが1982年に発表した「Front Line」という曲。82年っていうとそれこそ、モータウンが生み出したスター、マイケル・ジャクソンの「スリラー」がこの年に出ています。
スターが変わっていこうとしている時期なんですが、このときにStevie_Wonderは2枚組の「ミュージックエイリアム」っていうベストアルバムを出したんですね。ベストアルバムと言いながらも新曲が4曲含まれていて、その中の1曲がこの「Front Line」。最前線という意味ですね。
1982年っていうと、その前の年からレーガン大統領がアメリカのトップに就いて、世界的に見るとソ連との冷戦構造が激化している頃です。82年は南米の方でも紛争があって、軍靴の響きが大きくなってきたような時期。
そのときにミュージシャンとかアーティストっていうのは、炭鉱のカナリアとして、ちょっと世間一般よりも若干先駆けて危機的な状況をアナウンスするっていうことがあるわけですが、まさにこのStevie_Wonderの最前線と名付けられた「Front Line」という曲は、1964年に16歳という若さで志願兵としてベトナム戦争の戦地に行った人の話なんですね。
これもStevie_Wonderのストーリー作りのうまさが光る歌詞なんですが、ベトナムに行って、片足がぶっ飛んだと、お国のために。そういう自分というのは、若くて判断能力とかもさほど高くないときに、国からの圧力というか、そのムードで自分は最前線に立ったんだとフロントラインだったんだと。
こういう曲がもう出てこなくていいような世の中を作らなきゃいけないし、こういう曲を聞き続けなきゃいけないということでもあります。
スターが変わっていこうとしている時期なんですが、このときにStevie_Wonderは2枚組の「ミュージックエイリアム」っていうベストアルバムを出したんですね。ベストアルバムと言いながらも新曲が4曲含まれていて、その中の1曲がこの「Front Line」。最前線という意味ですね。
1982年っていうと、その前の年からレーガン大統領がアメリカのトップに就いて、世界的に見るとソ連との冷戦構造が激化している頃です。82年は南米の方でも紛争があって、軍靴の響きが大きくなってきたような時期。
そのときにミュージシャンとかアーティストっていうのは、炭鉱のカナリアとして、ちょっと世間一般よりも若干先駆けて危機的な状況をアナウンスするっていうことがあるわけですが、まさにこのStevie_Wonderの最前線と名付けられた「Front Line」という曲は、1964年に16歳という若さで志願兵としてベトナム戦争の戦地に行った人の話なんですね。
これもStevie_Wonderのストーリー作りのうまさが光る歌詞なんですが、ベトナムに行って、片足がぶっ飛んだと、お国のために。そういう自分というのは、若くて判断能力とかもさほど高くないときに、国からの圧力というか、そのムードで自分は最前線に立ったんだとフロントラインだったんだと。
こういう曲がもう出てこなくていいような世の中を作らなきゃいけないし、こういう曲を聞き続けなきゃいけないということでもあります。
この記事はいかがでしたか?
リアクションで支援しよう
radiko 防災ムービー「あなたのスマホを、防災ラジオに。」